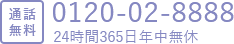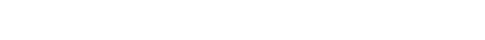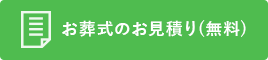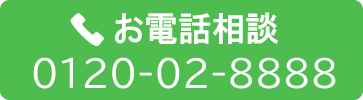浄土真宗とは?葬儀の流れや知っておくべきマナー・タブーを解説
公開日:2024/04/29
更新日:2024/11/28

浄土真宗とは、鎌倉時代に「親鸞聖人」が開いた仏教の宗派です。浄土真宗は、そのほかの仏教の宗派とは異なる独自の教えがあります。そのため、浄土真宗の葬儀を行う際や、浄土真宗の葬儀に参列する際は、浄土真宗の基本となる教えを理解したうえで、マナーや注意点を知っておくことが大切です。
この記事では、浄土真宗の歴史や教えをわかりやすく解説したうえで、浄土真宗の葬儀の流れやマナーを紹介します。浄土真宗の葬儀でタブーとされていることについても触れているので、ぜひ参考にしてください。
● 浄土真宗の特徴や教えを知りたい人
● 浄土真宗の葬儀の特徴を知りたい人
● 浄土真宗の葬儀の流れを知りたい人
● 浄土真宗の葬儀のマナー・タブーを知りたい人
浄土真宗とは?
浄土真宗とは、浄土教の一派であり、法然上人(ほうねんしょうにん)が開いた浄土宗の教えから派生した宗派です。浄土真宗は、法然上人の弟子となる「親鸞聖人(しんらんしょうにん)」が、鎌倉時代に開きました。現在の日本では、最も信者数が多い仏教宗派となっています。
浄土真宗の歴史
親鸞聖人は、比叡山にて20年の厳しい修行に没頭していましたが、修行を積んでも煩悩が消えることがなく、苦しんでいたといわれています。その後、比叡山を下り、浄土宗の開祖である法然上人と出会います。
そこで、法然が説く「南無阿弥陀仏の念仏を唱えることで、誰もが極楽浄土へ往生できる(専修念仏)」という教えに感銘を受け、法然上人の弟子となったのち、自らも浄土宗の教えを発展させた「浄土真宗」の開祖となりました。
浄土真宗の宗派
親鸞聖人によって開かれた浄土真宗は、親鸞聖人の没後、さらにさまざまな宗派に発展していきました。現在では「浄土真宗本願寺派」と「浄土真宗大谷派」が代表的な宗派となっています。
令和3年の文化庁「宗教年鑑」によると、浄土真宗本願寺派の信者数は約775万人、浄土真宗大谷派の信者数は約728万人であり、両宗派を合わせると、信者数は約1,500万人にのぼります。
浄土真宗の教え・浄土宗との違い
浄土宗の根本となる「南無阿弥陀仏の念仏を唱えることで、誰もが極楽浄土へ往生できる」という教えは、浄土真宗でも共通しています。
さらに、浄土真宗では「自己の力ではなく、阿弥陀仏の慈悲によって救われる(他力本願)」「阿弥陀仏の教えを信じるだけで救われる」「罪を自覚している悪人こそが、より阿弥陀に対する信仰心が強く救われる」といった教えを説いており、この点が浄土宗との違いといえます。
また、浄土真宗では「人は亡くなるとすぐに阿弥陀仏の救いによって極楽浄土に往生できる(即身成仏)」とされています。そのため、そのほかの宗派のように、故人の冥福を祈るといった慣習はありません。
この教えに基づき、浄土真宗の葬儀では、そのほかの宗派とは異なるマナーやタブー、注意点があります。
浄土真宗の経典
浄土真宗では、仏教で唱えられることの多い「般若心経(はんにゃしんきょう)」は経典とされていません。その理由は、般若心経が「修行や祈りによって自ら悟りを得て成仏する」という「自力」の教えに基づいているからです。
浄土真宗では「自己の力ではなく、阿弥陀仏の慈悲によって救われる」という「他力」の教えを軸としているため、般若心教ではなく独自の「浄土三部経」が経典とされています。
<浄土三部経>
● 大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)
● 観無量寿経(かんむりょうじゅきょう)
● 阿弥陀経(あみだきょう)
浄土真宗の葬儀の位置づけ
一般的に仏教の葬儀は、故人の冥福を祈る「供養」が目的となっています。しかし、浄土真宗では、「人は亡くなるとすぐに阿弥陀仏の救いによって極楽浄土に往生できる」という教えがあるため、葬儀も故人の供養が目的ではなく、阿弥陀仏へ感謝の気持ちを伝える儀式として位置づけられているのです。
また、亡くなった方は、誰もが極楽浄土へ往生できるため、再び仏となって再会できるとされています。そのため、別れの儀式を意味する「告別式」という名称も使用しません。
浄土真宗の葬儀の流れ
浄土真宗の葬儀の流れは、宗派によって異なります。ここからは「浄土真宗本願寺派」と「浄土真宗大谷派」での葬儀の流れを、具体的に解説します。
浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ
浄土真宗本願寺派の葬儀の一般的な流れは、以下のとおりです。
01.遺族・親族入場
02.導師入場
03.開式
04.帰三宝偈(きさんぽうげ)お経を唱える
05.念仏・合唱礼拝
06.三奉請(さんぶしょう)阿弥陀如来などの仏様をお招きするお経を唱える
07.導師焼香
08.正信偈(しょうしんげ)親鸞聖人が著した「教行信証」にある偈文を読経する
09.焼香
10.和讃(わさん)短い念仏を唱えて仏様をお送りする
11.回向(えこう)お勤めの終わりの文章を読み上げる
12.導師退場
13.閉式
14.喪主の挨拶
15.出棺
浄土真宗大谷派の葬儀の流れ
浄土真宗大谷派の葬儀は「葬儀式第一」と「葬儀式第二」に分かれているのが特徴です。
<葬儀式第一>
棺前勤行(かんぜんごんぎょう)と呼ばれる儀式を執り行います。従来は、斎場に出棺する前に自宅で行う儀式でしたが、現在では斎場で行うケースが増えています。
<葬儀式第二>
01.遺族・親族入場
02.導師入場
03.総礼(そうらい)参列者で合掌し念仏を唱える
04.勧衆偈(かんしゅうげ)お経を唱える
05.念仏 短念仏を10回唱える
06.回向(えこう)
07.総礼
08.三匝鈴(さんそうりん・さそうれい)鈴を鳴らす儀式を行う
09.念仏
10.三匝鈴
11.導師焼香・総礼
12.三匝鈴
13.正信偈(しょうしんげ)親鸞聖人が著した「教行信証」にある偈文を読経する
14.焼香
15.和讃(わさん)短い念仏を唱えて仏様をお送りする
16.回向(えこう)お勤めの終わりの文章を読み上げる
17.総礼
浄土真宗の葬儀のマナー
浄土真宗には、その他の宗派にはない独自の教えがあります。そのため、浄土真宗の葬儀に参列する際は、その教えを理解したうえで、事前に知っておくべきマナーがあります。ここでは、代表的な2つのマナーについて解説します。
香典袋の表書き
浄土真宗の葬儀では、香典袋の表書きには「御仏前」と書きます。
一般的に、仏式の葬儀では香典袋の表書きは「御霊前」と書きます。しかし、浄土真宗では、故人は亡くなられるとすぐに極楽浄土へ往生し、仏様になると考えられており、霊という概念はありません。
そのため、仏様に供えるという意味で「御仏前」を使用するのです。また、阿弥陀仏にお供えするという意味で「御供」と書く場合もあります。
焼香の仕方
仏式葬儀での焼香の一般的なやり方は、右手の親指、人差し指、中指の3本で抹香をつまみ、軽く頭を下げ、抹香をつまんだ右手を額に押しいただいてから、香炉の炭の上にくべます。
しかし、浄土真宗の焼香では、抹香を押しいただくことはせず、そのまま香炉の炭の上にくべます。また、焼香の回数は、浄土真宗本願寺派では1回、浄土真宗大谷派では2回となっています。同じ浄土真宗でも、宗派によって焼香の回数が異なるため、事前に執り行われる葬儀の宗派をよく確認しておきましょう。
浄土真宗の葬儀でやってはいけないタブー
上述の葬儀のマナーと同様に、浄土真宗の葬儀では、その教えに則り「やってはいけない」とされているタブーもあります。浄土真宗の葬儀は、阿弥陀仏へ感謝の気持ちを伝える儀式と位置付けられているため、事前にこうした注意点を理解して、適切な葬儀を執り行うことが大切です。
ここからは、浄土真宗の葬儀でやってはいけない5つのタブーについて解説します。
位牌を作る
位牌とは、故人の戒名などを記した札のことであり、故人の霊が宿るものとされています。しかし、浄土真宗では、故人は亡くなるとすぐに極楽浄土へ往生し仏になるという教えがあり、霊という概念がありません。
そのため、位牌を作ることはなく、代わりに「過去帳(または法名軸)」に故人の生前の名前と法名、亡くなった年月日を記録して仏壇に供えます。
冥福を祈る
一派的な葬儀では「冥福を祈る」という表現を使用することが多いでしょう。この「冥福を祈る」とは、故人が「死後の世界で迷うことなく、無事に浄土へたどり着くことを祈る」「死後の世界で幸せになることを祈る」という意味があります。
しかし、浄土真宗では、人は亡くなるとすぐに極楽浄土で往生するため、冥福を祈る必要がないのです。遺族や親族にご挨拶をする場面でも「ご冥福をお祈りします」ではなく「哀悼の意を捧げます」といった表現を使用しましょう。
末期の水の儀式を行う
末期の水の儀式とは、故人が亡くなったあとに、故人の口に水を含ませる儀式のことです。末期の水の儀式には「故人が苦しまず、安らかにあの世に旅立てるように」という意味が込められています。
しかし、浄土真宗では、亡くなった方は苦しみから解放されて浄土で仏になるとされているため、苦しみからの解放やあの世への旅立ちを意味する末期の水の儀式は行いません。
清めの塩を使用する
清めの塩は、さまざまな宗派の仏式葬儀で用いられています。清めの塩には「死は穢れ(けがれ)である」という考え方のもと、死に触れる葬儀のあとに、参列した方の穢れを払う役割があります。
浄土真宗では、故人はすぐに仏になるため、死に対して「穢れ」という概念がありません。そのため、清めの塩は用意しません。浄土真宗の葬儀で、清めの塩を用意してしまうと、故人に対して失礼になる場合もあるため注意しましょう。
ただし、参列される方には、それぞれ信仰する宗教や宗派があります。なかには「清めの塩が欲しい」とおっしゃられる方もいるでしょう。浄土真宗の葬儀を行う場合は、こうしたご希望者のための清めの塩の用意について、事前に葬儀社に相談しておくことをおすすめします。
線香を立てる
葬儀後に、ご仏前に線香をあげることもあるでしょう。浄土真宗では、線香をあげる際、線香は香炉に立てずに、手で折って横に寝かせて置きます。線香のあげ方もマナーのひとつであるため、あらかじめ理解して置くことも大切です。
浄土真宗の特徴や慣習を理解した上で葬儀に参列しましょう
浄土真宗とは、浄土宗の教えをもとに、親鸞聖人が鎌倉時代に開いた仏教の宗派です。現在の日本では、浄土真宗本願寺派と浄土真宗大谷派が主となっており、その信者数は約1,500万人にものぼります。
浄土真宗の教えは「南無阿弥陀仏の念仏を唱えることで、誰もが極楽浄土へ往生できる(専修念仏)」という浄土宗の教えをもとに「自己の力ではなく、阿弥陀仏の慈悲によって救われる(他力本願)」「人は亡くなるとすぐに阿弥陀仏の救いによって極楽浄土に往生できる(即身成仏)」という独自の教えがあります。
そのため、浄土真宗の葬儀では、そのほかの仏式葬儀とは異なるマナーや注意点があります。一般的な葬儀で行われている儀式がタブーとされていることもあるため、あらかじめ宗派の教えと、葬儀のマナーを理解しておくことが大切です。
メモリアルアートの大野屋では葬儀の事前相談を受け付けております。ベテランスタッフが常に待機しており、お客様それぞれの質問や、必要な事をお聞きした上で、お悩みに沿ったご提案やご相談をさせていただきます。ご納得いくまで何度でもご相談ください。