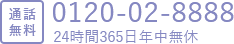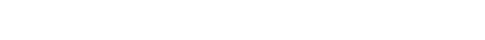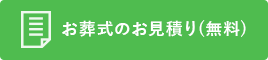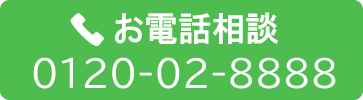ご遺体安置は自宅でできる?安置室と霊安室の違い、ご遺体安置の費用と期間を解説
公開日:2024/10/01
更新日:2024/10/01

葬儀が行われるまでの間、亡くなった方のご遺体をどこに安置すべきか、迷ってしまう方もいるでしょう。遺体安置の場所には、自宅や葬儀社・斎場の安置室といった複数の選択肢がありますが、それぞれに段取りや費用が異なります。
落ち着いて対応するためには、ご遺体の安置場所に加えて、安置期間や費用についても事前に知っておくことが大切です。
本記事では、遺体の安置場所の選び方から、安置室と霊安室の違い、費用相場や宗教別の安置方法まで、分かりやすく解説します。ぜひ最後までご覧いただき、後悔のない選択をするための参考にしてください。
● 遺体安置の場所を知りたい人
● 安置室と霊安室の違いを知りたい人
● 安置場所までの遺体搬送について知りたい人
● 遺体安置の費用や期間を知りたい人
● 死亡確認後から葬儀までに行われるケアや儀式を知りたい人
1.遺体安置とは
遺体安置とは、葬儀や火葬までの間、亡くなった方のご遺体を自宅や葬儀社の安置室などに保管しておくことを指します。
日本の法律では、死亡後24時間以内に火葬を行うことが禁止されています。そのため、少なくとも1日以上の遺体安置が必要です。この期間は、ご遺族が故人との最後の時間を過ごし、個人を偲ぶ大切な時間でもあります。
2.遺体安置の場所はどこ?
遺体安置の場所には、主に次の3つの選択肢があります。
・葬儀社や斎場の安置室
・民間業者の安置室
それぞれの特徴やメリット、デメリットについて見ていきましょう。
自宅での安置
自宅にご遺体を安置する方法は、故人を見守りながら、家族が最期の時間をゆっくり過ごせるという大きなメリットがあります。故人が慣れ親しんだ場所に安置することで、ご遺族にとっても心の負担が軽減されるでしょう。
ただし、自宅での安置には、搬入ルートや安置スペースの確保が必要です。また、自宅の場合、遺体安置のための設備が整っていないため、衛生管理やドライアイスの用意など、入念な準備が必要です。そのため、ご自宅で安置する場合でも、葬儀社にサポートを依頼することをおすすめします。
葬儀社や斎場の安置室
葬儀社や斎場の安置室にご遺体を安置する場合は、適切な設備が整った中でプロのサポートを受けられるため、ご遺族の負担が軽減されるというメリットがあります。とくに、自宅での安置が難しい場合や、衛生面・管理面での心配がある場合には、葬儀社や斎場の安置室をおすすめします。
また、葬儀社や斎場の安置室を利用する場合は、専門的な知識を有するスタッフが対応してくれるので、安心して故人をお任せできるでしょう。ただし、施設の使用料がかかるため、自宅安置に比べると費用がかさむこともあります。また、葬儀社や斎場によっては、故人との面会時間に制限があるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
民間業者の安置所
民間業者の安置所とは、自宅や葬儀社・斎場の安置室を使用できない場合に利用される施設です。24時間営業の施設が多く、ご遺族はいつでも故人と面会できるのがメリットです。最近では、宿泊施設が整った安置所もあり、故人のそばで過ごすこともできます。
ただし、葬儀社に比べると民間業者の安置所は数が少なく、自宅や斎場から遠方になってしまう可能性もあります。
3.安置室と霊安室の違いとは?
ご遺体を保管する場所には「安置室」のほかに「霊安室」があります。似ている言葉ですが、それぞれ目的や使用されるシーンが異なります。
安置室は、ご遺体を火葬や葬儀までの間、適切に保管するために用意された専用の部屋です。主に、葬儀社の施設内や斎場内に設置されています。安置室には、ご遺体の保管に必要な設備が整っており、遺族が面会に訪れることもできます。また、故人を弔いながら、静かな時間を過ごせる場所です。
一方「霊安室」は、病院内に設けられた一時的な遺体保管場所です。霊安室は、病院で亡くなった方のご遺体を、安置場所(自宅や葬儀社・斎場の安置室)に搬送するまでの限られた時間、保管するためのスペースです。2〜3時間前後の利用が一般的で、長期の安置はできません。
4.安置場所への遺体搬送の段取り
現代の日本では、多くの方が病院で亡くなります。病院で亡くなった方のご遺体は、院内の霊安室で一時的に保管されたあと、安置場所へ搬送されます。
ここでは、安置場所への遺体搬送の段取りについて解説します。
安置場所の決定
ご遺体を一時的に霊安室に保管している間、まずは安置場所を決定します。
ご遺体を安置する場所は、自宅や葬儀社の安置室、民間業者の安置所があげられます。それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで、ご遺族の意向や状況に応じて最適な場所を選ぶことが大切です。
安置場所を決定する際は、故人の意思を尊重しつつ、ご遺族や親族が集まりやすい場所を選びましょう。安置場所で悩んだ際は、葬儀社のスタッフに相談することをおすすめします。
遺体搬送車の手配
安置場所が決まったら、次にご遺体を搬送する車両を手配します。
病院から自宅や安置室への遺体搬送は、葬儀社が手配する専用の車(寝台車など)を利用するのが一般的です。ご遺体の搬送には、専門的な知識や設備が必要になるためです。
ご遺族が自家用車で搬送すること自体は、法律で禁止されてはいません。しかし、自家用車で搬送中にご遺体を損傷してしまったり、目的地とは異なる場所に行ってしまったりすると、法律で罪に問われる可能性があります。そのため、ご遺族が自家用車で搬送するのは難しいといえるでしょう。
死亡診断書の受け取り
ご遺体を安置場所に移す際には、死亡診断書の受け取りが必要です。死亡診断書は、医師が故人の死亡を確認した際に発行される重要な書類です。
診断書は、遺体搬送前に病院の担当者から受け取ります。死亡診断書は火葬許可証を申請する際や埋葬の際にも必要になるため、紛失しないように注意しましょう。
近親者・菩提寺への連絡
ご遺体の搬送準備が整ったら、近親者や菩提寺への連絡を行います。近親者には、安置場所の詳細を伝えて弔問のスケジュールを調整します。とくに、遠方にお住まいの方は、移動に時間がかかり宿泊を伴う可能性もあるため、早めに連絡しましょう。
また、菩提寺を持つ檀家の場合は、菩提寺の住職が安置場所で枕経をあげることがあります。そのため、安置場所が決まったら、菩提寺への連絡も忘れずに行いましょう。
5.遺体安置の期間と費用
亡くなった方のご遺体は、日本の法律により、死後24時間以内に火葬を行うことが禁止されています。そのため、少なくとも1日以上の安置が必要です。一般的な安置期間は、ご逝去から2〜3日間ですが、火葬場の予約状況や六曜との関係(友引は火葬場が休業になるなど)によっては、安置期間が延びる場合もあります。
遺体安置の費用相場は、安置場所によって異なります。一般的な目安金額をまとめました。
| 安置場所 | 費用相場(2日間想定) |
| ご自宅 | 3万円~7万円 |
| 葬儀社や斎場の安置室 | 5万円~15万円 |
| 民間業者の安置所 | 3万円~10万円 |
自宅での遺体安置の費用には、以下のものが含まれます。
・搬送費用:1万5,000円~3万円前後(10Km前後)
また、搬送用の寝具や枕飾りの準備を葬儀社に依頼すると、別途3〜5万円前後の費用が掛かります。
葬儀社や斎場の安置室、民間業者の安置所は、自宅での安置よりも費用が高くなる傾向があります。これは、上記のドライアイス代や搬送費用にプラスして、施設使用料が追加されるためです。施設使用料の目安は以下のとおりです。
・民間業者の安置所:1万円前後/日
また、葬儀社や斎場の安置室、民間業者の安置所の場合、付き添いの費用が別途発生する場合もあるため、詳しくは葬儀社のスタッフなどに相談してみましょう。
6.宗教別の遺体安置方法
ご遺体の安置方法は、故人の宗教や信仰によって異なる場合があります。ここでは、代表的な例として、仏教、神道、キリスト教の安置方法をご紹介します。
仏教の遺体安置
日本では、仏教が最も広く信仰されている宗教であり、遺体安置も仏教の形式に則って行われるのが一般的です。
仏教では、ご遺体を安置する際は、ご遺体の頭を北向き、または西向きにして横たえることが基本とされています。ご遺体の手には数珠を持たせ、合掌させます。また、枕元には「枕飾り」と呼ばれる仏具やお供え物を置き、故人を弔います。
神道の遺体安置
神道では、仏教とは異なり、ご遺体の頭を西向き、または東向きにして安置します。ご遺体の顔には白い布をかけ、手は合掌させます。枕元には御霊代やお供え物を置いた「枕飾り」を供えます。
キリスト教の遺体安置
キリスト教では、教派や地域によって安置方法が異なりますが、基本的にはご遺体の頭を北向きにして安置します。カトリックもプロテスタントも、ご遺体の顔を白い布で覆うのが一般的です。仏教のような枕飾りはありませんが、臨終の儀式の際に用いたものを枕元に供えることもあります。
また、教派によっては、遺体安置の間に親族や信者が集まり、賛美歌を歌ったり聖書を読んだりして祈りを捧げます。
上記は一般的な安置方法であり、それぞれ宗派や教派によっても異なります。そのため、事前に故人の宗教に合わせて、必要なものや段取りを確認しておくといいでしょう。
関連記事:
枕飾りはいつどのように行うか?宗教別に飾り方や必要なもの、注意点を解説
7.死亡確認後から遺体安置・葬儀までに行われる儀式やケア
故人が亡くなったあと、ご遺体が安置場所へ搬送される前後に、いくつかの儀式やケアが行われることがあります。これらは、故人を敬い、最期の時間を大切に過ごすという重要な意味を持ちます。ここでは、代表的な儀式やケアをご紹介します。
末期の水
「末期(まつご)の水」は、故人が亡くなった直後に行われる儀式で、家族が故人の口元を少量の水で湿らせるものです。この儀式には、亡くなった方が旅立つ前に、最後に水を口にすることで、故人の安らかな旅立ちを願うという意味が込められています。「末期の水」の由来は諸説ありますが、仏教の開祖であるお釈迦様が入滅するまえに、最後に口にされた水に由来するといわれています。
本来はご逝去の直前に行われる儀式でしたが、現在ではご逝去後に病室で行うのが一般的です。ただし、安置場所に搬送してから行うケースもあります。
湯灌の儀、清拭
「湯灌(ゆかん)の儀」とは、故人の体をぬるま湯で清める儀式のことです。従来は、ご遺族がご自宅で行っていましたが、現在は病院で亡くなるのが一般的となったため「湯灌の儀」を行わず「清拭(せいしき)」と呼ばれるケアを看護師が行うケースが増えています。「清拭」とは、ご遺体の全身をアルコールに浸した脱脂綿などで清潔に拭くケアのことです。
「清拭」ではなく「湯灌の儀」を希望する場合は、あらかじめ葬儀社に相談をしたうえで、湯灌師などの専門のスタッフに依頼しましょう。
着替え、死化粧
「湯灌の儀」や「清拭」で故人の体を清めたあとは、故人が旅立つための準備として、死装束への着替えや死化粧が行われます。
死装束は、宗教によって形式が異なります。また、一般的な死装束ではなく、故人が生前に好んでいた服などに着替えることも可能です。
死化粧とは、故人が安らかな姿で眠れるように、髪や表情、身だしなみを整え、顔に自然な美しさを取り戻すための化粧を施すケアです。死化粧をすることで、ご遺族は故人との最後の別れをより穏やかに迎えることができるでしょう。
関連記事:
死装束は左前?右前?着せ方や装具の種類、宗教での違いを解説
エンゼルケア
エンゼルケアとは、医療現場で行われるご遺体のケアのことで、一般的には、上述の「清拭」や「着替え」「死化粧」を含む一連のケアのことを指します。
エンゼルケアは、亡くなった方に敬意を払いながら、安らかで美しい状態を保つための重要なステップです。また、故人のご遺体を整える意味に加え、ご遺族の心のケアにもつながります。
エンバーミング
エンバーミングとは、ご遺体の長期間保存を目的とした特殊な処置のことです。ご遺体を殺菌・消毒したうえで、血液や体液を専用の薬剤と入れ替えるといった化学的な処置を施します。この処置により、ご遺体の腐敗を遅らせ、見た目の状態を保つことができます。
エンバーミングは、事故や病気で生前の姿と大きく異なる場合や、海外で亡くなったなど葬儀までの日数がかかる場合に行われるケアです。エンバーミングは専門の技師が行うため、希望する際は、葬儀社に相談しましょう。
関連記事:
「湯灌の儀」とは? 〜その意義や手順、「エンバーミング」「死に化粧」「エンゼルケア」との違いを解説〜
8.ご遺体安置の場所や流れを理解して、後悔のない方法を選びましょう
故人が亡くなられたあとは、葬儀・火葬までの間、ご遺体を安置する必要があります。日本では、法律で臨終後24時間は火葬ができません。そのため、少なくとも1日以上はご遺体の安置が必要です。
遺体安置の場所は、ご自宅のほか、葬儀社・斎場の安置室、民間業者の安置所などがあります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり、費用も異なるため、葬儀社に相談しながら適切な安置場所を決定しましょう。この記事を参考に、遺体安置の場所選びや流れを理解して、後悔のない方法を選んでください。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀の事前相談を受け付けています。ご遺体の安置方法でご不明な点がありましたら、ぜひお問合せください。