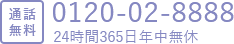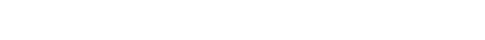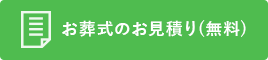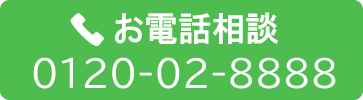余命宣告をされたら?心構えややるべきこと、準備や手続きなどを解説
公開日:2024/10/24
更新日:2024/10/24

大切な家族が余命宣告を受けたとき、どう対処すれば良いのか迷われる方は多いでしょう。治療方針の選択や、これから進めるべき準備には、精神的にも大きな負担が伴います。
そこで本記事では、余命宣告を受けた際の具体的な準備や、家族と過ごす時間を大切にするためのサポート方法を解説します。本人や家族の気持ちに寄り添いながら、穏やかに日々を過ごすための参考にしていただければ幸いです。
● 余命宣告の意味を知りたい人
● 余命宣告を受けた際の心構えを知りたい人
● 余命宣告を受けた際にやるべきことを知りたい人
● 家族が余命宣告を受けた際にかける言葉を知りたい人
1.余命宣告とは?
余命宣告とは、医師が患者の病気の進行状況を評価し、今後どの程度の期間が残されているかを患者や家族に伝える行為です。一般的には、末期がんや深刻な疾患が進行している場合に行われます。余命宣告では「〇ヵ月」や「〇年」といった具体的な期間を告げられる場合もあれば「〇年〜〇年」と幅を持たせる場合もあります。
ただし、余命宣告はあくまで統計的なデータに基づく推定であり、個々の病状によって大きく異なる可能性があります。そのため、必ずしも余命宣告で伝えられた期間通りになるとは限りません。治療の進展や患者の体調次第で、余命が前後することもあります。
生存期間中央値とは?
余命宣告では「生存期間中央値」という概念が用いられることがあります。生存期間中央値は、同じ病状の患者の中で「50%の人がその期間内に亡くなり、残りの50%がそれを超えて生存する期間」を指します。
この中央値をもとに余命の見通しが伝えられますが、必ずしも個々のケースに正確に当てはまるものではない点に注意しましょう。
余命宣告の形はさまざま
余命宣告は、医師が直接患者に伝える場合や家族のみに伝える場合など、さまざまな形があります。どのように伝えられるかは、本人の意向や家族の希望、医師の判断によって異なります。
余命宣告を受ける際には、医師と家族とのコミュニケーションを密にし、余命宣告の意味を正しく理解することが大切です。
2.家族が余命宣告されたときの心構え
大切な家族が余命宣告を受けたときは、本人も家族も精神的に大きなショックを受けることでしょう。しかし、本人が少しでも心穏やかに過ごすためには、家族のサポートが欠かせません。
そこでここからは、ご家族が余命宣告されたときの心構えと、具体的なサポート方法について解説します。
まずは病気について正しい理解を
余命宣告を受けた際、家族が病気についての正しい知識を持つことは非常に重要です。医師からの説明をしっかり聞き、患者の病状や今後の治療方針について理解を深めましょう。
また、病状について不明点があれば、医師に積極的に質問することも大切です。家族が病気の進行や治療について理解することで、患者とのコミュニケーションも取りやすくなり、より適切なサポートができるようになるでしょう。
本人との接し方、かける言葉に注意
余命宣告を受けたあと、本人にどのように接するかは非常に繊細な問題です。過剰な励ましや悲観的な言葉は避け、患者の気持ちに寄り添った対応を心がけましょう。
「がんばって」などの軽率な応援の言葉や「余命宣告なんて当てにならない」などの根拠のない言葉は、本人にプレッシャーを与えてしまったり、苛立ちの原因になったりする可能性があります。本人が穏やかに過ごすためにも、感情的な言葉をかけないように注意しましょう。
本人も悲観的な気持ちになり、涙を流してしまうことも少なくありません。そういった場合は、無理に言葉をかけるのではなく、家族として寄り添い、気持ちに共感するだけでも本人の支えとなるはずです。
本人がやりたいことを実現するためのサポート
残された時間が少ない可能性があると知ったとき、本人が「やりたいこと」を実現できるように家族はサポートしてあげましょう。
例えば、友人との再会、趣味の活動、思い出の地を訪れるなど、可能な範囲で本人が希望することをできるように医師と相談しながら、対応を考えます。本人がやりたいことを実現する過程の中で、家族も一緒に大切な時間を過ごせるでしょう。
自己のケアも大切に
患者を支える家族は、時に自分のケアをないがしろにしがちです。しかし、長期間のサポートは、家族の心身にも大きな負担がかかります。
そのため、ご自身の健康にも配慮し、家族全員で相談しながら無理のないサポート体制を整えることが大切です。また、つらい現状を家族だけで抱え込むのではなく、医師や看護師、専門のカウンセラーなどに相談したり、サポートサービスを利用したりすることも検討しましょう。
3.余命宣告されたら、まずは治療・医療行為の方針の選択を
余命宣告されたら、まずは治療や医療行為についての方針を選択します。医師と相談しながら、患者本人や家族の意向に沿った最善の方針を決めましょう。
治療や医療行為の選択肢には、主に次のようなものがあります。
・延命治療
・完治を目指した治療の継続
・緩和ケア
・セカンドオピニオン
1つずつ詳しく見ていきましょう。
延命治療
延命治療とは、病気を治すための治療ではなく、余命を少しでも延ばすための医療行為のことです。主な延命治療の方法には、人工呼吸や人工栄養、人工透析などがあげられます。
延命治療は「もうすぐ生まれる孫に、ひと目会いたい」「子どもの結婚式が近いので、それまでは一緒に過ごしたい」など、本人にとって大切なライフイベントを家族と一緒に迎えたい場合や、家族と少しでも長く過ごしたい場合に検討される選択肢です。
ただし、延命治療は本人の身体に負担がかかるため、患者の体力や意向を十分に確認した上で選択することが重要です。
完治を目指した治療の継続
余命宣告は、症状の回復が難しく、医師が手を尽くしても「これ以上の治療が難しい」と判断された場合に行われます。しかし、まれに余命宣告を受けたとしても、新薬や新しい治療法が残されている場合もあります。
ただし、こうした新薬や新しい治療法には、副作用の可能性があったり、金銭的な負担が大きくなったりするデメリットも存在しています。治療が長引くことで、本人も家族も精神的な負担が大きくなるかもしれません。
家族が治療の継続を望む場合でも、本人の意思を尊重したうえで、医師と相談して慎重に判断しましょう。
緩和ケア
緩和ケアは、延命を優先せず、患者の痛みや苦しみを軽減し、生活の質を保つことを目的とした治療です。本人の身体的な負担を最小限にしながら、家族と一緒に穏やかな時間を過ごしたいと考える場合に選択されることが多い方法です。
具体的には、薬によって痛みを軽減するケアや栄養管理、水分補給、呼吸のサポート、カウンセリングによる精神的なサポートなどがあげられます。
緩和ケアは、病院だけではなく自宅でも受けられる場合があります。ただし、家族の適切な介護やサポートが必要になることもあるため、医師や看護師との連携を大切にしましょう。
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンとは、別の医師に診断や治療方針を確認することで、異なる意見や別の治療の可能性を探る方法です。最初の診断に不安や迷いを感じている場合や、他の選択肢を探したい場合の方法としてあげられます。
ただし、セカンドオピニオンを受ける場合でも、主治医の診断内容や治療方針を十分に理解しておくことが大切です。
4.余命宣告されたら準備すべきこと・やるべきこと
余命宣告を受けたあとは、治療方針の選択だけでなく、家族や本人が具体的にどのような準備を進めていくかを考えることが大切です。これにより、残された時間を大切に過ごすための基盤を整え、穏やかな気持ちで日々を過ごすことができるでしょう。
ここでは、余命宣告後に準備すべきこと・やるべきことについて解説します。
親族や友人・知人に伝えるか考える
余命宣告を誰に伝えるかは慎重に考える必要があります。患者本人の意思を最優先にして、告知する範囲やタイミングを決めましょう。
親族や友人、知人には、必ず伝えなければならないというわけではありません。本人が他者に知らせたくない場合は、その意向を尊重することが重要です。少しずつ段階的に伝えたり、必要に応じて特定の人にのみ伝えたりするという方法もあります。
保険の確認
生命保険や医療保険に加入している場合、その内容を確認して、適用される保障内容を把握しておきましょう。とくに、生命保険に「リビングニーズ特約」を付加していれば、余命6カ月以内と診断された場合に、保険金の全部(または一部)を生前に受け取ることができます。
リビングニーズ特約で受け取った保険金は、治療費や生活費だけでなく、残された時間を充実させるための資金としても役立てることが可能です。
金融機関の口座や各種契約の確認
金融機関の口座やクレジットカード、各種契約の状況なども整理しておきましょう。とくに、本人しか分からない暗証番号や契約情報がある場合は、家族が把握できるようにしておくことが大切です。
また、金融機関の口座は、名義人である本人が亡くなった場合、その事実が金融機関に伝わると凍結されてしまいます。凍結後は相続手続きが完了するまで、口座からお金を引き出すことができなくなるため、生活費や葬儀費用の準備が難しくなることがあります。事前にお金を引き出しておくなどの対策をしておきましょう。
相続・財産の確認
相続や遺産分割に関する準備も忘れないようにしましょう。とくに、遺産が多い場合や法的なトラブルを避けたい場合は、弁護士や税理士と相談し、相続の手続きをスムーズに進めるための準備を整えておくことが望まれます。
遺言書やエンディングノートを活用し、財産の分配について家族と話し合っておくことをおすすめします。
遺言書やエンディングノートの作成
遺言書とは、法的効力を持ち、相続人や財産分配についての本人の意思を明確に示す文書です。遺言書を作成することで、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、家族がスムーズに手続きを進めることができます。
法的効力を持つ遺言書を作成するためには、法律に基づいた手続きが必要です。そのため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家のサポートを受けることをおすすめします。
一方、エンディングノートには法的効力はありませんが、本人の意思や希望を記載し、家族に伝えるための手助けとなります。たとえば、葬儀の希望や残したいメッセージ、感謝の気持ちなどを、整理して書きのこすことができます。また、本人がエンディングノートに「やりたいこと」「行きたい場所」などを書き出すことで、残された時間を有意義に過ごす道しるべとなるでしょう。
エンディングノートと遺言書を組み合わせることで、より詳細な意思を家族に伝えることができます。
関連記事:
終活とは?やることチェックリストや始めるべきタイミングを解説
葬儀の準備
「存命中に葬儀の話をするのは縁起が悪い」と考える方もいるかもしれませんが、あらかじめ葬儀について準備をしておくことで、ご逝去の際に遺族の負担を軽減できます。また「本人の意思を尊重した葬儀を実現できる」という大きなメリットもあるのです。
葬儀の準備では、葬儀の形式や規模、参列者の範囲などを検討しておきましょう。なじみは少ないものの「生前葬」という選択肢もあります。生前葬は、本人が存命中に自らの葬儀を執り行うもので、本人の希望を反映できるだけでなく、感謝の気持ちを直接伝える場としても注目されています。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀の事前相談を受け付けています。ぜひご相談ください。
写真を撮る
余命宣告を受けたあと、本院と家族が一緒に過ごす時間を大切にするために、思い出に残る写真を撮ることも検討してみましょう。家族や友人と過ごす時間を記録に残すことは、本人にとっても家族にとっても、大きな心の支えになるでしょう。
デジタルデータの整理
近年では、インターネット上のデジタルデータやサブスクリプション契約の管理も重要になっています。本人のSNSアカウントの情報やオンラインサービスの契約を整理し、必要に応じて解約手続きを進めましょう。
また、デバイスやクラウドに残されている画像や写真、文章などのデータも、必要に応じてバックアップを取ります。本人が「他人には見られたくない」「もう必要がない」と判断したデータは削除しておくのがおすすめです。
メモリアルアートの大野屋の「もしも会員」にご登録いただくと、もしもの時の費用面での割引特典はもちろん、元気な今から活用できる「相続相談」や「家系図作成」「ご自宅の安全見守り」など、さまざまな提携特典をご利用いただけます
5.「終活」は人生を悔いなく過ごすための大切なもの
余命宣告を受けたあとの準備ややるべきことは「終活」にもつながります。終活とは、人生の最終段階に向けて自分の意思や希望を整理し、残された家族の負担を軽減するための準備を進める活動です。
財産の整理や葬儀の準備に限らず、エンディングノートを活用して医療や介護に関する希望を記録したり、デジタル遺品を整理したりすることも含まれます。また、やりたいことリストを作成し、残された時間を悔いなく過ごすための行動計画を立てることも終活の一環です。
終活に取り組むことは、残された時間を有意義に過ごせるだけでなく、本人と家族の気持ちを落ち着け、穏やかに過ごすことの一助となるでしょう。
関連記事:
終活とは?やることチェックリストや始めるべきタイミングを解説
メモリアルアートの大野屋とベストファームグループ 東京シルバーライフ協会がタッグを組んで安心サービス「大野屋の老後生活サポート」をご提供しています。
6.【まとめ】余命宣告を受けたときに大切なこと
余命宣告を受けた本人やご家族にとって、精神的な負担は非常に大きなものです。しかし、準備や手続きを進めることは、残された時間を穏やかに過ごすための大切なステップとなります。
治療方針の選択や日常生活の整理を通じて、本人の希望を尊重し、家族との時間を大切にすることができるでしょう。また、適切な準備を進めることは、本人の不安や家族の負担を軽減し、心穏やかな日々を送る手助けとなります。
ぜひこの記事を参考に、ご家族での大切な時間をお過ごしください。