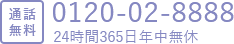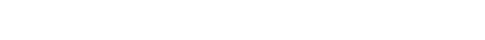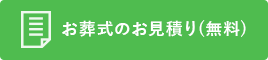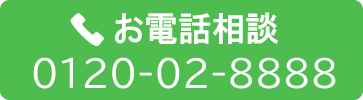「玉串料(たまぐしりょう)」とは? 初穂料との違い、金額相場、包み方やマナーについて解説
公開日:2024/12/17
更新日:2024/12/17

● 「玉串料」とは何かを知りたい方
● 玉串料にいくら包めばよいか迷っている方
● 神式葬儀と仏式葬儀の違いを知りたい方
1.玉串料とは?
「玉串料(たまぐしりょう)」とは、神式の儀式において神様にお供えする金銭のことをいいます。たとえば神式葬儀の場合は、遺族が葬儀を執り行う神職や神社へ納める謝礼金や参列者が遺族にお渡しする金銭のことを指し、仏式葬儀の「お布施」や「香典」に近い役割を果たすものです。神式の葬儀に参列する際は、仏式葬儀で香典を包むのと同様に「玉串料」を包んで持参します。
もともと神道では、神様に祈りや感謝の気持ちを伝えるお供えものとして、榊(さかき)の枝に紙垂(しで)をつけた「玉串」を捧げて拝礼する儀式が行われてきました。しかし、時代の流れとともに儀式の参列者が自身で玉串を用意して持参することが難しくなってきたため、代わりに「玉串料」としてお金を納めることが一般的になってきたのです。
玉串料は、葬儀などの弔事に限らず、お宮参りや七五三、結婚式といった慶事の他、神社で行われる祭礼や祈祷、地鎮祭など、さまざまな儀式で用いられますが、この記事では主に葬儀に関連する事柄を中心に解説します。
2.玉串料と初穂料・お布施の違いは?
神社へ納めるお金としては、「玉串料」の他に、「初穂料(はつほりょう)」と呼ばれるものもあります。葬儀においては、宗教者にお渡しするお金といえば、「お布施(ふせ)」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。いずれも玉串料と混同されやすい言葉ですが、それぞれ意味合いが大きく異なり、間違って用いるとマナー違反となってしまうため注意が必要です。ここでは、玉串料と初穂料、お布施との違いについて解説します。
■ お布施との違い
お布施とは、僧侶に読経をしていただいたり、戒名をつけていただいたりしたお礼の気持ちとしてお渡しする金銭のことです。日本で行われる葬儀のほとんどが仏式であることから、実際に渡した経験はなくても言葉の意味をなんとなく知っているという方も多いのではないでしょうか。宗教者にお渡しする金銭という意味では玉串料と似ていますが、お布施は仏教の教えにもとづくものであるため神道では用いません。
■ 初穂料との違い
神社で特別な祈願をお願いするときやお札やお守りを授かるときなどに、「初穂料」を納めた経験がある方もいらっしゃると思います。「初穂」とは、その年に初めて収穫されたお米のことをいい、かつては収穫の感謝を込めて神様に初物の農作物を奉納する風習がありました。これが由来となって、現代では玉串と同様、収穫物の代わりに「初穂料」として金銭をお供えすることが一般的となっています。
神様に捧げる金銭という意味では、玉串料と初穂料は同じものといえますが、使う場面には注意が必要です。前述した通り、初穂料は神様に「感謝の気持ち」を伝えるものであり、葬儀などの弔事に用いるのは不適切とされています。お宮参りや七五三、結婚式といった慶事にのみ使いましょう。一方、玉串料は、慶事、弔事のどちらにも用いることができます。ただし、どちらに使用しても問題ないとされてはいるものの、お守りやお札を受ける際や慶事の場では「初穂料」を用いることのほうが多いようです。
3.玉串料の金額相場
神式葬儀の参列者がご家族にお渡しする玉串料の相場は、仏式葬儀における香典の相場と同じと考えていただいて構いません。因みに、慶事においても、たとえば神社での挙式と会食に出席する場合、一般的なチャペルなどの挙式と披露宴に出席する際のご祝儀と同等に考えれば問題ないでしょう。
以下に、神式葬儀を含め、神社に納める玉串料の一般的な金額相場をまとめました。ただし、ご祈祷の内容や神社によっても納める金額は異なります。神社のホームページなどに記載している場合もありますので、ご祈祷の内容とお願いする神社が決まったら事前に確認してみるとよいでしょう。相場がわからず不安な場合は、神社に直接尋ねても問題ありません。
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| お宮参り | 5千〜1万円 |
| 七五三 | 5千〜1万円 |
| 結婚式 | 5〜10万円 |
| 地鎮祭 | 3〜5万円 |
| 厄払い | 5千〜1万円 |
| 神式葬儀 | 30万〜40万円 |
| 霊祭・式年祭(法要) | 3〜5万円 |
4.玉串料を包む封筒・水引の選び方、書き方
玉串料を持参するときは、どのような封筒に包み、表書きは何を記入すればいいのでしょうか。ここでは、玉串料を入れる封筒や水引の選び方、表書きの正しい書き方などをご紹介します。
■ 封筒の選び方
玉串料を包む封筒は、シーンによって使い分けが必要です。具体的には、お宮参りや七五三、婚礼などの慶事、葬儀・告別式などの弔事、厄払いや地鎮祭など各種お祓いと、大きく三つに分けられます。
慶事には紅白、弔事には黒白、お祓いには白無地の封筒を用いることが一般的です。弔事で玉串料を包む場合は、黒白の不祝儀袋を用意しましょう。ただし、蓮の花やユリの花がデザインされた不祝儀袋は、神式葬儀には用いません。蓮の花は仏教、ユリの花や十字架はキリスト教にまつわるものであるため、神道の葬儀に持参するのはマナー違反となります。
■ 水引について
神式葬儀に参列する際は、仏式の香典にあたる「玉串料」を不祝儀袋に包んで持参します。表書きは、「玉串料(または御玉串料)」、「御榊料」、「「御神前」などとします。蓮の花が描かれた不祝儀袋は仏式用であるため、神道の葬儀では無地のものを選びましょう。水引は、黒白または双銀、双白の結び切りのものを用います。
水引は、用途に合わせた「色」や「形」のほか、包む金額に見合ったものを選びます。水引が封筒にプリントされたものは1万円くらいまで、それよりも金額が高い場合は実際に水引が使われているものを選ぶとよいでしょう。たとえば、結婚式などで5万円を超えるような金額を包む場合は、より豪華な装飾のものを選ぶと中身と封筒とのバランスがとれて違和感がありません。
弔事の場合、水引の「色」は、黒白、双銀(銀一色)、双白(白一色)を用います。玉串料の場合、慶事では紅白の水引を用いることが一般的です。水引の「形」にはさまざまな種類がありますが、そのうち祝儀袋・不祝儀袋に多く用いられるものに「結び切り」と「蝶結び」があります。ほどけにくい「結び切り」は何度も繰り返すことがないよう願う事柄に、ほどいて結び直すことができる「蝶結び」は何度起こってもうれしい事柄に使われます。そのため、弔事では不幸が重ならないようにという意味合いから「結び切り」の水引を使用します。
参考までに、慶事の場合は「蝶結び」が基本ですが、婚礼については"結婚を繰り返す"ことにならないようという意味で、「結び切り」の水引を選ぶことがマナーです。また、お祓いや祈祷では白い無地の封筒を使うことが基本ですが、神社や地域によっても考え方が異なり、地鎮祭や竣工式などの際は、慶事と同じ紅白の水切りがついた祝儀袋を使用するケースもあります。
どんなタイプを選べばよいかわからないときは、地域の人や神社に相談してみるとよいでしょう。
| シーン | 封筒 | 水引の色・形 |
|---|---|---|
| 弔事 | 黒白の不祝儀袋 | 黒白・双銀・双白 結び切り |
| 慶事 | 紅白の祝儀袋 | 紅白 蝶結び (ただし婚礼は結び切り) |
| 各種お祓い | 白無地の封筒 | なし (ただし地域や神社による) |
■ 表書き・中袋の書き方
目的に合った封筒を用意したら、次に表書きや中袋に必要な項目を書きましょう。以下に、それぞれの書き方や注意点について解説します。
【表書きの書き方】
慶事・弔事を問わず、のしの上段に名目、下段に名前を書くのが基本です。慶事・弔事ともに表書きは「玉串料」または「御玉串料」とし、下段にフルネームを書きます。市販の祝儀袋や不祝儀袋には、あらかじめ表書きが印刷されているものが多いので、用途に合ったものを選ぶことが重要です。筆記具は、筆または筆ペンを使用し、慶事の場合は濃墨、弔事の場合は薄墨で書きましょう。
記入する名前は、弔事では贈り主の名前を書きます。一方、お宮参りや七五三の場合は子どもの名前、お祓いやご祈祷の場合は受ける人の名前を書くことが一般的です。
連名で贈る場合、3名まではそれぞれのフルネームを書きます。2名の場合は中央に並んで、3名の場合は中央から左に向かって目上の人から順に記入しましょう。4名以上の連名で贈るときは、代表者のフルネームを中央に書き、その左側に「外一同」または「他一同」と書き添えます。
【中袋の書き方】
市販の祝儀袋・不祝儀袋には、お金を入れる「中袋」がついていることが一般的です。中袋の表面には金額を、裏面の左下に住所・氏名を記入します。2〜3名の連名で贈る場合は全員分の住所・氏名を書きますが、連名者が多い場合は別紙に全員分の住所・氏名を書いて中袋に入れましょう。中袋がない場合は、封筒に直接お金を入れて表書きをし、裏面の左下に住所と金額を書きます。
金額を記入するときは、「大字(だいじ)」と呼ばれる漢数字の旧字体を用いるのがマナーです。たとえば、10,000円を包む場合は「金壱萬円也」と書きます。
【金額に漢数字の旧字体を用いる理由】
祝儀袋・不祝儀袋に旧字体の漢数字で金額を書く理由は、読み間違えや改ざんを防ぐためといわれています。たとえば、普段使用している「一、二、三」という漢数字は簡略化されているため、「壱、弍、参」という旧字体に比べて読み間違えてしまう可能性があり、線を簡単に書き足すだけで意味合いが変わってしまうので数字を改ざんされるリスクがあるためです。現代の漢数字を用いてはいけないというわけではありませんが、一般的なマナーとしても、不要なトラブルが生じてお相手に迷惑がかかることを避けるためにも、旧字体の漢数字で書くことをおすすめします。
日常的に書き慣れていない方がほとんどかと思いますので、祝儀袋・不祝儀袋に記入する際は表記の間違いや書き損じがないよう気をつけましょう。以下に対応表をまとめましたので、ぜひお役立てください。
| 数字 | 漢数字(現代) | 漢数字(旧字体) |
|---|---|---|
| 1 | 一 | 壱 |
| 2 | 二 | 弍 |
| 3 | 三 | 参 |
| 5 | 五 | 伍 |
| 10 | 十 | 拾 |
| 1000 | 千 | 阡、または仟 |
| 10000 | 万 | 萬 |
5.封筒に入れるお札のマナーや注意点
祝儀袋や不祝儀袋に入れる際は、お札の選び方や入れ方にもマナーがあります。慶事と弔事でも異なり、いつも迷ってしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか。玉串料を包む際の基本的なルールは、仏式葬儀や一般的な結婚式などの場合と変わりません。慶事、弔事それぞれの違いを理解しておくと、一般的な知識としてきっと役立つことと思います。
■ 慶事の場合(表側・上に肖像画)
慶事の場合は、封筒の表面と、お札の表面(肖像画が印刷されている)の向きを合わせます。そして、お金を出すときに最初に肖像画があらわれるように、肖像画が上部になる向きで入れましょう。お札は、新札を用意するのが一般的です。 外袋で包むときは、先に上側を折り、下側を上に折って重ねます。「天を仰ぎ、幸せを受け止める」様子をイメージするとわかりやすいかもしれません。
■ 弔事の場合(裏側・下に肖像画)
弔事では、基本的には慶事と逆にするのがマナーです。封筒の裏面に、お札の表面(肖像画が印刷されている)が向くようにお金を入れます。お金を出したときに肖像画が見えないように、肖像画が下部(封筒の底)に位置する向きで入れましょう。
弔事の場合、事前に不幸のために用意していたと思われないよう、お札は新札でないものにするとよいといわれています。ただし、汚れたり破れたりしているなど、あまりにも状態が良くないものは避けたいところです。最近は弔事に新札を使っても問題ないと考える方も増えていますが、従来の慣習を気にされる方もいらっしゃることをふまえて、新札しか用意できない場合は折り目を付けてから入れると安心です。
外袋で包むときは、先に下側を上に折ってから、上側を下に折ってかぶせます。「不幸は上から下へ流す」というイメージを持つと覚えやすいかもしれません。
| シーン | お札の向き | 紙幣 |
|---|---|---|
| 慶事 | 表側・上に肖像画 | 新札 (きれいなお札) |
| 弔事 | 裏側・下に肖像画 | 使用感のあるお札 (新札の場合は折り目をつける) |
6.神式葬儀と仏式葬儀の違い
神式の葬儀は「神葬祭(しんそうさい)」と呼ばれ、仏式同様2日間にわたって行われます。仏式の葬儀・告別式にあたる儀式を「葬場祭(そうじょうさい)」、通夜にあたる儀式を「通夜祭(つやさい)」といいます。神式葬儀には、日本で多く行われている仏式葬儀とは異なる儀式や作法があるので、初めて参列する場合は不安に思うかもしれません。ここでは、神式葬儀に参加する際の注意点と、覚えておきたい作法について解説します。
■ 仏式葬儀との違い
神道の死生観では、亡くなった人の魂は家にとどまり子孫の守り神になると考えられています。死は悲しむべきものではないため、神式葬儀では「お悔やみ申し上げます」といった悲しみをあらわす言葉は用いません。また、「冥福」、「成仏」、「供養」といった言葉は仏教用語であり、神式葬儀では不適切です。仏式葬儀に欠かせない数珠も、仏具であり神道では使いません。神式葬儀に参列するときに持参することは控えましょう。
仏式葬儀で行われる読経や焼香は神式葬儀では行わず、読経の代わりに神職が祝詞を捧げます。そして、仏式葬儀の焼香にあたるのが「玉串奉奠(たまぐしほうてん)」という儀式です。玉串奉奠については、以下に詳しく解説します。
■ 玉串奉奠とは
「玉串奉奠」とは、神道の儀式において玉串を神前に捧げる行為のことをいいます。「玉串拝礼(たまぐしはいれい)」もほぼ同じ意味で使われますが、厳密には、玉串を捧げるまでを「玉串奉奠」、玉串を捧げた後の拝礼までを含めた行為を「玉串拝礼」といいます。
神式葬儀で行われる玉串奉奠の儀式では、参列者が玉串を祭壇に捧げて故人の霊が安らかであるようにと祈ります。神道において、玉串は特別な意味を持つものです。玉串奉奠の作法を以下にまとめましたので、神式葬儀に参列する際はぜひ参考になさってください。
■ 玉串奉奠の作法
1. 斎主と親族に一礼し、玉串を受け取る。右手で玉串の枝を上からつまむように持ち、左手で葉先を下から支えるように持つ。
2. 時計回りに90度回転して枝を手前にし、左手を枝、右手を葉先に持ち替える。
3. 持ち替えたら時計回りに180度回転し、枝を祭壇に向けて供える。
4. 一歩後ろに下がり、2回深く礼をし、2回柏手を打ち、再び深く礼をする(二礼二拍手一礼)。数歩下がり、斎主と遺族に一礼し、自分の席に戻る。
その他、神式葬儀の流れや儀式については、こちらの記事でも解説しています。
7.玉串料について要点まとめ
● 「玉串料(たまぐしりょう)」とは、神式の儀式において神様にお供えする金銭のこと。
・神式葬儀において、仏式葬儀における「お布施」や「香典」にあたるものと考えるとよい
・玉串料と同じく神社に納める「初穂料」は弔事には不適切とされ、慶事のみに用いる
● 弔事には黒白、慶事には紅白、お祓いには白無地の封筒を用いることが基本。
・蓮の花やユリの花が印刷された不祝儀袋は、他宗教用であり神式葬儀には不適切
・慶事・弔事ともに表書きは「玉串料」または「御玉串料」とし、下段にフルネームを書く
● 神式葬儀を「神葬祭」といい、通夜・告別式にあたる「通夜祭」と「葬場祭」が営まれる。
・仏具である数珠は神式葬儀には不要。「冥福」「成仏」「供養」といった仏教用語も使わない
・神式葬儀では焼香は行わず、「玉串奉奠」と呼ばれる玉串を神前に捧げる儀式が行われる
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常に待機しております。それぞれの宗教や宗派の葬儀や法要について、お客様それぞれのご状況をお伺いし、お悩みに沿ったご提案をさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。