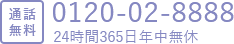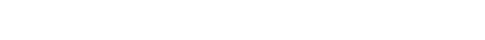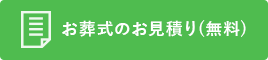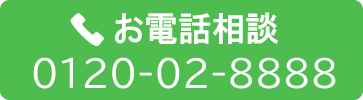浄土宗とは?葬儀の特徴と知っておくべきマナー・注意点を解説
公開日:2024/12/20
更新日:2024/12/20

浄土宗は、平安時代末期に法然上人が開いた仏教の宗派の1つです。「南無阿弥陀仏」という念仏を唱えることで、誰もが極楽浄土に往生できるという「専修念仏」の教えが中心となっています。
この記事では、浄土宗の歴史や考え方、経典の特徴を解説するとともに、浄土宗の葬儀の流れやマナー、戒名について詳しく紹介します。浄土宗の教えや葬儀について知りたい方や、参列する機会がある方は参考にしてください。
● 浄土宗の概要や歴史などを知りたい人
● 浄土宗の考え方や経典(お経)を知りたい人
● 浄土宗の葬儀の特徴や流れを知りたい人
● 浄土宗の葬儀のマナーや注意点を知りたい人
● 浄土宗の戒名について知りたい人
1.浄土宗とは?
浄土宗は、平安時代末期である1175年に法然上人(1133年〜1212年)によって開かれた仏教の宗派です。現在の日本でも、浄土真宗に次いで信者数の多い宗派となっています。
法然上人は、比叡山での修行を通じて、多くの人々が救われる道を模索した僧です。平安時代末期は争いが絶えず、社会が荒廃し、人々は修行すらままならない状況にありました。法然上人は、そうした人々でも救われる方法がないかと考え、比叡山の奥深くにこもり、一切経を読み込みました。
その中で「ただ念仏を唱えるだけで極楽浄土に往生できる」という教えを見出し、これを「専修念仏」として広めたといわれています。
浄土宗の総本山・七大本山の寺院
浄土宗の総本山は、京都市東山区にある「知恩院」です。ここは法然上人の入滅の地としても知られています。
さらに、浄土宗には「七大本山」と呼ばれる七つの主要な寺院が存在します。
・増上寺(東京都 港区)
・金戒光明寺(京都府 京都市 左京区)
・百萬遍知恩寺(京都府 京都市 左京区)
・清浄華院(京都府 京都市 上京区)
・善導寺(福岡県久 留米市)
・光明寺(神奈川県 鎌倉市)
・善光寺大本願(長野県 長野市)
浄土宗の本尊は「阿弥陀如来」です。阿弥陀如来は、無限の光明と寿命を象徴する仏であり、浄土宗では人々を極楽浄土に導く存在とされています。
浄土宗と浄土真宗との違い
浄土宗と浄土真宗は、どちらも阿弥陀如来への信仰を中心とした仏教の宗派ですが、その教えや実践には違いがあります。
浄土宗は、法然上人によって開かれ「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えることで極楽浄土への往生を目指す教えです。念仏の回数や方法に特別な制限はなく、行動や善行も重要とされています。
一方、浄土真宗は、法然上人の弟子である親鸞聖人によって、鎌倉時代の中期に開かれました。浄土真宗では、阿弥陀仏の救いにすべてをゆだねる「他力本願」の考えが強調され、念仏は感謝の表現として行われます。そのため、浄土宗のように念仏を唱えること自体が修行として位置付けられることはありません。
また、浄土宗では僧侶が出家者として厳しい戒律を守るのに対し、浄土真宗には戒律はありません。そのため、浄土真宗の僧侶は、結婚をして家族を持つことが認められているなど、僧侶の在り方にも違いがあります。
こうした違いは、同じ阿弥陀如来を信仰の中心に据えながらも、それぞれの宗派が独自の発展を遂げてきたことを示しています。
2.浄土宗の考え方、経典(お経)の特徴
浄土宗の教えの中心には「南無阿弥陀仏」と唱えることによって阿弥陀如来の慈悲を信じ、極楽浄土への往生が叶うという「専修念仏」の考え方があります。
法然上人は、このシンプルな修行法を提唱し、どのような状況の人でも念仏を唱えることで救われると説きました。この教えは、当時の社会的背景からも広く支持され、多くの人々の信仰の対象となりました。
「南無阿弥陀仏」の意味
「南無阿弥陀仏」は、阿弥陀如来を信じ、その慈悲に心を寄せて救いを願う念仏です。
「南無」はサンスクリット語の「ナモー(namas)」に由来しており、「帰依する」や「礼拝する」という意味を持ちます。「阿弥陀仏」は阿弥陀如来を指しています。
浄土宗では、この念仏を唱えることで阿弥陀如来の慈悲による救済を得られると信じられています。
浄土宗の経典(お経)の特徴
浄土宗で重視される経典は「浄土三部経」と呼ばれる三つの経典です。具体的には「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」がそれに該当します。
無量寿経
法蔵菩薩が阿弥陀如来となり、極楽浄土に往生した話を中心に、浄土教信仰を体系的に記したお経。
観無量寿経
古代インドの王妃・韋提希夫人に釈迦が説いた教えを中心に、極楽浄土に行く方法が記されたお経。
阿弥陀経
極楽浄土の様子や極楽浄土に行く方法が説かれているお経。
これらの経典は、阿弥陀如来の慈悲や極楽浄土の詳細を記したものであり、浄土宗での念仏の重要性を理解する上で欠かせないものとされています。
3.浄土宗の葬儀の特徴
浄土宗の葬儀では、念仏を唱える儀式が中心に行われ、故人が阿弥陀如来の慈悲によって極楽浄土へ往生できるよう祈ります。中でも「念仏一会(ねんぶついちえ)」「下炬引導(あこいんどう)」といった儀式が特徴的です。
念仏一会
念仏一会は、参列者全員が「南無阿弥陀仏」と唱える象徴的な儀式です。南無阿弥陀仏を繰り返し唱えることで、故人の極楽浄土への往生を祈ります。
念仏を唱える回数に明確な決まりはありませんが、一般的には僧侶の言葉に従い、10回以上の一定回数を唱えます。
下炬引導(あこいんどう)
下炬引導は、僧侶が2本のたいまつ(または線香などの法具)を持ち、そのうちの1本を捨て、残った1本で円を描き、下炬の偈(げ)を読み上げたあと、その1本も捨てる儀式です。
下炬引導は「厭離穢土(おんりえど)」という仏教の思想に基づいています。「厭離穢土」とは「この穢れた世を離れる」という意味で、現世の苦しみや煩悩を断ち切ることを意味しています。
たいまつを捨てる動作や僧侶による引導の言葉を通じて、故人が煩悩から解放され、平安に旅立てるよう祈りが捧げられます。
4.浄土宗の葬儀の流れ
浄土宗の葬儀は、以下のような流れで進行します。
・香偈(こうげ):お香を焚き、心を鎮めるための儀式が行われます。
・三宝礼(さんぼうらい):仏、法、僧の三宝に対して礼拝を捧げます。
・奉請(ぶじょう):仏様を葬儀の場にお迎えする儀式です。
・懺悔偈(さんげげ):仏様に罪を懺悔し、故人の安らかな往生を願います。
・作梵(さぼん):僧侶が「四智讃(しちさん)」を唱え、仏の知恵を称えます。
・下炬引導(いんどうあこ):上述のとおり。
・開経偈(かいきょうげ):教義の真髄を理解し、故人が仏教の教えを受け入れることを願う儀式です。
・読経(どっきょう):「四誓偈」または「仏心観文」の経文を読誦します。
・念仏一会(ねんぶついちえ):上述のとおり。
・総回向(そうえこう):念仏の功徳を故人に捧げ、極楽浄土への往生を願います。
・三身礼(さんじんらい):阿弥陀仏への帰依を誓い、礼拝を捧げます。
・送仏偈(そうぶつげ):仏様を本来の居所へ送り届ける儀式が行われます。
・退堂(たいどう):僧侶と参列者が退場し、儀式が終了します。
これらの流れを通じて、参列者は故人への祈りを捧げ、故人が安らかに旅立つことを願います。
5.浄土宗の葬儀の知っておくべきマナー・注意点
浄土宗の葬儀に参列する際には、マナーや注意点を理解しておくことが大切です。以下に焼香や香典、服装の主なポイントを紹介します。
焼香のマナー・注意点
浄土宗の葬儀の焼香には、厳密な決まりごとはありません。焼香回数は3回、または1回が一般的です。
お香は右手の親指と人差指、中指の3本の指でつまみ、左手を添えながら額の高さまで持ち上げると同時に、軽く頭を下げ祈ります。香を額に近づける必要はありません。お香を香炉に入れたあと、合掌して一礼します。
香典のマナー・注意点
浄土宗の香典の表書きには、一般的な仏式葬儀と同じく「御霊前」や「御香典」が用いられます。浄土宗では故人が仏となるのは四十九日以降とされているため、葬儀時点では「御仏前」ではなく「御霊前」が一般的です。
金額は地域や関係性によって異なりますが、親族であれば1万円〜3万円前後、友人や知人であれば5千円程度が目安です。
服装のマナー・注意点
服装についても、一般的な葬儀のマナーと大きな違いはありません。男性、女性共に喪服を着用しましょう。
男性の場合は、ブラックフォーマルのスーツに黒無地のネクタイ、白のワイシャツ、黒の靴下、黒の革靴を合わせます。
女性の場合は、ブラックフォーマルのスーツやワンピースに黒の透け感のあるストッキング、黒の光沢のないパンプスを合わせます。スカートの場合は、ひざが隠れる程度の長さのものを着用し、トップスは胸元が開きすぎていないものを選んでください。
6.浄土宗の葬儀のお布施のマナー・注意点
お布施とは、葬儀の読経や戒名授与を行う僧侶に対して、感謝の気持ちを示すためにお渡しする金銭のことです。
お布施の金額に明確な決まりはなく、地域性や僧侶との関係性によっても異なりますが、一般的には10万円〜30万円が目安とされています。また、お布施のほかに、交通費に相当する「御車料」や、会食に参加されない場合は「御膳料」をお渡しすることもあります。
お布施は、葬儀の開始前に渡すのが一般的です。僧侶に直接渡す場合は、袱紗(ふくさ)に包んでお持ちし、お渡しする直前に袱紗から出して切手盆にのせて渡します。切手盆がない場合は、袱紗の上に乗せてお渡しします。袱紗もなく封筒のままお渡しするのは失礼になるので注意してください。
開始前にお渡しできなかった場合は、葬儀終了後にお渡しします。
お布施や御車料、御膳料の金額や準備について悩んだ場合は、葬儀社に相談してみることをおすすめします。
7.浄土宗の戒名について
戒名とは、故人が仏門に入った証として与えられる名前で、浄土宗をはじめとする多くの仏教宗派で用いられます。日本では、出家した方や在家僧侶の方を除き、多くの場合は亡くなられた際に戒名が授けられます。
浄土宗の戒名は、院号・誉号・戒名・位号の順で構成されており、故人の生前の人柄や功績を反映して付けられます。
・院号(いんごう)
故人の社会的地位や功績を称える特別な名称です。院号は特に高位の戒名に付けられます。
・誉号(よごう)
故人の人格や功績を表す称号です。この誉号は、ほかの宗派には見られない浄土宗特有の形式です。
・戒名(かいみょう)
仏門に帰依した名前で、一般的には故人の生前の名前や性格、信仰の深さに基づいて付けられます。
・位号(いごう)
故人の性別や地位を示します。男性の場合は「居士」、女性の場合は「大姉」が一般的です。特別な功績がある場合は「信士」「信女」などが用いられることもあります。
戒名のランクや内容は、地域や寺院、僧侶との関係によって異なるため、事前に相談しておくことが重要です。また、戒名をいただく場合は、お布施(戒名料)を納めます。
8.浄土宗の教えや葬儀の内容を把握して、故人を穏やかにお見送りしましょう
浄土宗は「南無阿弥陀仏」の念仏を唱えることで極楽浄土に往生できるとする「専修念仏」の教えが特徴です。その教えは、葬儀の儀式や戒名の形式にも反映され、故人の極楽浄土への往生を祈る厳かな儀式が行われます。
この記事を通じて、浄土宗の基本的な知識や葬儀の流れを把握し、正しいマナーで大切な方をお見送りする準備を整えてみてはいかがでしょうか。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常に待機しております。葬儀や法要について、お客様それぞれのご状況をお伺いし、お悩みに沿ったご提案をさせていただきますので、いつでもお気軽にご相談ください。