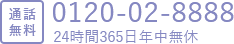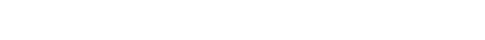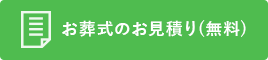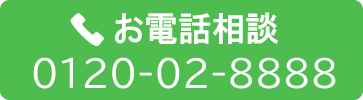真言宗とは?葬儀の特徴や流れ、知っておくべきマナー・注意点を解説
公開日:2025/01/08
更新日:2025/01/10

真言宗は密教の一派であり、仏教の中でも特に深遠な教えを持つ宗派です。開祖・空海(弘法大師)によって日本に伝えられ、その教えは「即身成仏」の思想を中心に、日常生活と仏教の実践を深く結びつける特徴があります。
本記事では、真言宗の歴史や教えについて解説するとともに、真言宗の葬儀の流れやマナー、注意点についても詳しくご紹介します。真言宗の儀式の意味や作法を知り、葬儀に臨む際の参考にしてください。
● 真言宗の概要や歴史などを知りたい人
● 真言宗の考え方や経典(お経)を知りたい人
● 真言宗の葬儀の特徴や流れを知りたい人
● 真言宗の葬儀のマナーや注意点を知りたい人
1.真言宗とは?
真言宗は平安時代初期、806年に空海(弘法大師、774年〜835年)によって開かれた仏教の宗派です。
密教の教えを修得した空海(弘法大師)
空海は804年に唐(現在の中国)に渡り、長安にて「密教」の教えを学びました。密教は、言葉だけでなく、体や心の感覚を通じて教えを師から弟子に口伝で伝え、深い悟りに至る実践を重視する教派です。密教の教えのすべてを修得した空海は、日本に帰国した後「真言宗」を開き、高野山を中心に全国にその教えを広めたとされています。
空海の生きた時代は、桓武天皇による平安京への遷都(794年)や蝦夷征討が進められた変革期でした。また、遣唐使による大陸との文化交流が盛んで、空海自身もこの流れの中で唐に渡っています。
このような激動の時代において、空海は密教の教えを通じて、宇宙や生命の本質に迫る思想を提唱しました。真言宗の教えは、深遠な思想と実践を組み合わせることで、多くの人々に救いを提供することを目的としています。
ご本尊は「大日如来」
真言宗の中心となる御本尊は「大日如来(だいにちにょらい)」です。真言宗では、大日如来は宇宙の真理そのものを象徴しているとされており、すべての仏や菩薩の源とされる存在と考えられています。
真言宗では、この大日如来を通じて宇宙の真理や永遠の智慧(ちえ)を体現することが、信仰の中心となっています。
真言十八本山とは
真言宗には多くの宗派があり、それぞれが独自の教えや伝統を持っています。代表的なものだけでも18の宗派が存在し、各宗派には大本山と呼ばれる中心的な寺院が設けられています。それが「真言十八本山」です。
「真言十八本山」は、信仰の拠点として多くの人々に親しまれ、真言宗の教えを伝える重要な役割を担っています。代表的な寺院には、高野山金剛峯寺や京都の東寺(教王護国寺)などがあります。
2.真言宗の考え方、経典・お経の特徴
真言宗の教えの中心には「即身成仏」という考え方があります。これは「人間は、この身のまま仏となる可能性を持っているという」思想であり、修行や実践を通じて悟りに至る道を示しています。
真言宗が広まる以前の仏教では「成仏(仏となること)」は来世で到達するものとされ、長い修行や転生を経た後に達成されるという考えが一般的でした。
一方、真言宗の「即身成仏」は、現世において、修行や密教儀式を通じて悟りを得ることができると説いています。
真言宗で使う経典
真言宗では、多くの密教経典が修行や儀式で使用されます。代表的な経典として以下が挙げられます。
・般若理趣経(はんにゃりしゅきょう)
・大日経(だいにちきょう)
・金剛頂経(こんごうちょうぎょう)
・蘇悉地羯羅経(そしつじからきょう)
・瑜祇経(ゆぎきょう)
・要略念珠経(ようりゃくねんじゅきょう)
これらの中でも、真言宗で多く用いられる特徴的な経典が「理趣経」です。理趣経は、密教の根本的な教えを記した経典であり、人間の煩悩や欲望を肯定的に捉え、それを悟りへと昇華する道を説いています。
「理趣経」では、欲望や執着も修行の一環として活用できるとされ、その実践が真言宗の修行において重要な役割を果たしています。
真言宗で唱える言葉
真言宗では、宗派ごとに独自の言葉が唱えられます。以下に代表的なものを紹介します。
高野山真言宗
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)
醍醐派
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)
南無聖宝尊師(なむしょうぼうそんし)
南無神変大菩薩(なむじんぺんだいぼさつ)
御室派
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)
南無禅定法皇(なむぜんじょうほうおう)
智山派
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)
南無開山興教大師(なむかいさんこうぎょうだいし)
豊山派
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)
南無興教大師(なむこうぎょうだいし)
南無専誉僧正(なむせんよそうじょう)
南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)は「空海(弘法大師)に帰依する」という意味で、開祖である空海への敬意を表しています。
また、各宗派ごとに「南無大師遍照金剛」に加えて、それぞれの宗派に縁の深い僧への敬意を表す言葉も用いられます。これは、各宗派が空海(弘法大師)を中心にしつつも、独自の歴史や思想を反映していることを示しています。
3.真言宗の葬儀の特徴
真言宗の葬儀は、故人を「密厳浄土」と呼ばれる理想の世界へ送り届けるための儀式が中心となります。この浄土は、大日如来が統べる悟りの世界であり、真言宗の教えを象徴する存在とされています。
真言宗の葬儀では、独特の儀式が執り行われ、仏教の深遠な教えと結びついた荘厳な形式が特徴です。その中でも特に重要とされるのが「土砂加持(どしゃかじ)」と「灌頂(かんじょう)」です。
土砂加持(どしゃかじ)について
土砂加持は、故人を清め、「密厳浄土」へ送り届けるために行われる真言宗特有の儀式です。この儀式では、清められた特別な土砂を用いて護摩焚きを行います。護摩焚きの最中には、災いを払うとされる光明真言(こうみょうしんごん)が唱えられます。
護摩焚きで使用した土砂は、儀式後に納棺前のご遺体に振りかけられます。これは「滅罪生善(めつざいしょうぜん)」と呼ばれ、生前の罪を消し去り、苦悩を取り除くと考えられています。
灌頂(かんじょう)について
灌頂は、故人の魂を清め、仏の世界へ導く真言宗の葬儀の象徴的な儀式です。灌頂では、僧侶が清浄な水を故人の頭部に少量を注ぐことで、仏との一体化を祈願します。この水には、悟りの境地を開く力があると信じられています。
4.代表的な真言宗の葬儀の流れ
真言宗の葬儀では、密教の教えを反映した独特の儀式が行われます。真言宗には多くの宗派があり、宗派ごとに葬儀の流れは異なりますが、ここでは代表的な例を紹介します。
1. 僧侶の入場と身を清める準備儀式
僧侶は、葬儀を行うにあたり、心身を清める以下の準備儀式を行います。
塗香(ずこう):お香を体に塗り、穢れを取り除きます。
洒水(しゃすい):清水を振りまいて場を浄化します。
三密観(さんみつかん):身・口・意を仏に集中させる瞑想法です。
護身法(ごしんぼう):五種の印を結び、真言を唱えることで心身を守ります。
加持香水(かじこうずい):特別に祈祷された香水を用いて浄化を行います。
2. 仏様を迎え入れる儀式
故人を浄土へ導くために仏を迎え、儀式の成功を祈ります。
三礼(さんらい):仏法僧に対して三度礼拝し、敬意を表します。
表白(ひょうびゃく):故人の救済を祈願し、仏菩薩に願いを述べます。
神分(じんぶん):仏や菩薩の加護を故人に授ける祈りを行います。
声明(しょうみょう):仏典に節をつけて唱える仏教音楽で、祈りを深めます。
3. 授戒の儀式
故人が仏の教えに帰依することを象徴する重要な儀式です。
剃髪(ていはつ):故人の頭を剃り、仏門に入る準備を整える儀式(現在は形だけの場合が多い)。
授戒(じゅかい):故人に戒名を授け、仏の教えを守る者としての帰依を表します。
4. 引導の儀式
故人が仏の世界へ旅立つことを助けるための重要な儀式です。
表白(ひょうびゃく)と神分(じんぶん):故人の魂の救済を願い、祈りを再度捧げます。
不動灌頂・弥勒三種の印:故人の即身成仏が果たされます。
5. 墓前作法
故人が煩悩を離れ、悟りの境地へ至ることを祈願します。
破地獄(はじごく):地獄の苦しみを取り除き、心の平安を祈ります。
位牌開眼・血脈授与:位牌に故人の魂を迎え入れ、仏とつながる縁を築きます。
6. 焼香と出棺
最後の祈りと見送りを行います。
焼香:参列者が故人への祈りを込めて焼香を行います。
導師最極秘印:僧侶が印を結び、故人を仏の世界へ送り出します。
出棺:最後に故人を花で飾り、お別れの言葉を捧げて旅立ちを見送ります。
5.真言宗の葬儀の知っておくべきマナー・注意点
真言宗の葬儀に参列する際は、宗教的な伝統や習慣に則った作法やマナーを理解しておくことが重要です。ここでは、特に注意すべきポイントを解説します。
真言宗葬儀の焼香の作法
真言宗では、焼香を3回行うのが正式な作法です。その際、香を額の高さまで押しいただき、香炉にくべます。ただし、参列者の数が多い場合や進行上の都合によっては、焼香を1回に短縮する場合もあります。以下に具体的な流れを説明します。
祭壇に進む
自分の順番が来たら、静かに祭壇に進みます。進む際には、僧侶やご遺族、参列者に軽く一礼を行います。
焼香台の前で一礼と合掌
焼香台の前に立ったら、一礼をしてから合掌を行います。このとき、数珠を右手にかけ、房を下にして両手で挟むように持つのが正式な作法です。
焼香を行う
右手の親指、人差し指、中指の3本の指で抹香を軽くつまみ、額の高さまで押しいただいてから、香炉にくべます。この動作を3回繰り返すのが基本です。参列者の数が多い場合などでは、1回に短縮する場合があります。
合掌と退席
焼香が終わったら、再度合掌をして祈りを捧げます。その後、静かに2〜3歩下がってから僧侶やご遺族、参列者に一礼をして席に戻ります。
真言宗葬儀の香典の包み方
真言宗の葬儀で使用する香典袋の表書きは、「御霊前」または「御香典」が一般的です。親族の場合は1万円から10万円、友人や会社関係者の場合は5,000円程度が相場とされています。四十九日を過ぎた場合には「御仏前」に変更します。
中袋には金額を漢数字で記載し、名前と住所を併記します。複数人で用意する際は「〇〇一同」と記載し、個別の名前や金額、住所を明記した明細を添えるのが適切です。
香典袋は袱紗に包んで持参し、渡す際には袱紗から取り出して丁寧に手渡します。香典に関しては、真言宗独自の決まりはありませんが、基本的なマナーを守ることで失礼のない対応ができます。
真言宗葬儀の数珠の使い方
真言宗では数珠が信仰の象徴として特に重視されており、本式の「振分数珠(ふりわけじゅず)」が用いられます。振分数珠は、主珠が108個、親珠には2本ずつ房が付く形式で、煩悩を断ち切り仏道に導く教えを象徴しています。
振分数珠は左手に二重にして持ち、親珠を上に、房を自然に垂らします。合掌時には両手の中指に振分数珠をかけ、房が外側に垂れるようにするのが基本的な作法です。正しい持ち方を心がけることで、真言宗の教えへの敬意を示すことができます。
ただし、参列者が振分数珠を用意できない場合は「略式数珠」を使用しても問題ありません。略式数珠は、どの宗派でも使用可能な汎用的な形式です。ただし、略式数珠であっても、振分数珠と同様に持ち方などには注意を払いましょう。
数珠の色や素材は、茶系統や黒が一般的ですが、女性用には水晶が選ばれることもあります。
真言宗葬儀のお布施のマナー
真言宗の葬儀におけるお布施は、僧侶への感謝や読経のお礼として渡す金銭を指します。相場は通夜から初七日までで10万円から30万円程度とされますが、戒名料を含む場合は金額が大きく変わることがあります。戒名のランクによっては数百万円に達する場合もあるため、事前に寺院や親族に確認することが重要です。
お布施は奉書紙や無地の白封筒に包み、表書きには「お布施」と記載し、下段に喪主の名前を記載します。金額は旧字体の漢数字で記入し、筆ペンまたは毛筆を使用するのがマナーです。渡す際は直接手渡しせず、切手盆または袱紗を使用しましょう。
また、僧侶の交通費として「御車代」、会食を辞退された場合の「御膳料」などを別途用意する場合があります。それぞれ白封筒に包み、適切なタイミングでお渡しするように心がけましょう。
真言宗葬儀の服装のマナー
真言宗の葬儀に参列する際は、黒の喪服を着用するのが一般的です。真言宗独自の注意点やマナーはないため、男性はブラックフォーマルのスーツ、女性はブラックフォーマルのスーツや黒のワンピースを着用しましょう。
また、男性は白シャツに黒ネクタイ、黒の革靴を合わせるのが基本です。女性は、透け感のある黒ストッキングに黒のパンプスを合わせましょう。スカートの場合は、ひざが見えない長さのものを着用してください。
アクセサリーは控えめにし、派手な金や銀の装飾品は避けましょう。髪型も清潔感を大切にし、髪が長い方は1つにまとめるのが一般的です。
6.真言宗の教えを知り、葬儀の特徴や流れを把握しておきましょう
真言宗は「即身成仏」の教えを中心に、深遠な密教の思想に基づいた儀式が行われる宗派です。真言宗の葬儀では、故人を「密厳浄土」へ送り届けるための独特な儀式が執り行われ、その中で「土砂加持」や「灌頂」などが重要な役割を果たします。焼香や数珠に関しても、特有の作法があります。
この記事を通じて、真言宗の葬儀の流れやマナーを理解し、大切な方を心を込めてお見送りする準備を整えてください。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。