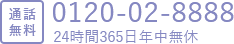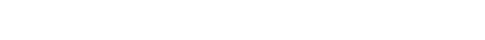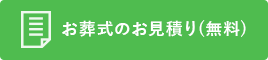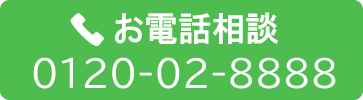天台宗とは?葬儀の特徴と流れ、知っておくべきマナー・注意点を解説
公開日:2025/01/14
更新日:2025/01/14

天台宗は、日本仏教のなかでも歴史が古い宗派のひとつです。開祖・最澄(伝教大師)が比叡山延暦寺を拠点に教えを大成し、この地が「日本仏教の母山」と呼ばれるほど多くの宗派の開祖を輩出したことでも知られています。
本記事では、天台宗の起源や歴史、教えの特徴に触れながら、天台宗の葬儀の流れや押さえておきたいマナー・注意点をわかりやすく解説します。天台宗の儀式の意味や作法を知り、葬儀に臨む際の参考にしてみてください。
● 天台宗の概要や歴史などを知りたい方
● 天台宗の考え方や経典(お経)を知りたい方
● 天台宗の葬儀の特徴や流れを知りたい方
● 天台宗の葬儀におけるマナーや注意点を知りたい方
1.天台宗とは?
天台宗は、日本仏教のなかでも歴史の古い宗派のひとつです。その教えは中国の天台大師・智顗(ちぎ)によって説かれた天台の教義を基盤としており、平安時代初期に最澄(伝教大師)によって日本へと伝えられました。
天台宗は、法華経を重んじながらも、密教的な要素を取り入れるなど、多面的な特徴をもっています。まずは、天台宗の起源や歴史を見ていきましょう。
日本の天台宗の開祖「最澄」
天台宗の開祖である最澄(767年〜822年)は、近江国(現在の滋賀県)に生まれ、若くして比叡山に入山します。804年には遣唐使として唐(現在の中国)に渡り、天台の教えをはじめ、さまざまな仏教理論を学びました。
帰国後、最澄は比叡山を拠点に「誰しもが悟りを開く可能性をもつ」という平等性を重視した「一乗思想(いちじょうしそう)」を説き、806年には朝廷の勅許を得て正式に天台宗を開きます。
その後、比叡山を仏教の総合大学のような学問・修行の場と位置づけ、日本各地に天台の信仰を広めていきました。
天台宗の総本山「比叡山延暦寺」
天台宗の総本山である比叡山延暦寺は、滋賀県大津市と京都市の境に広がる比叡山にあり、最澄が開いた「一乗止観院」がその始まりとされています。現在では「古都京都の文化財」として世界遺産にも登録されており、多くの参拝者や観光客が訪れる場所となっています。
比叡山延暦寺は「日本仏教の母山」とも呼ばれており、ここで修行を積んだ僧侶のなかからは、法然(浄土宗)や親鸞(浄土真宗)、栄西(臨済宗)、道元(曹洞宗)、日蓮(日蓮宗)といった諸宗派の開祖たちが輩出されました。
また、比叡山延暦寺では「千日回峰行(せんにちかいほうぎょう)」などの厳しい修行も受け継がれており、日本仏教における重要な拠点として今もなお大きな存在感を放っています。
2.天台宗の考え方、経典・お経の特徴
天台宗は法華経を重視しており「人はみな仏性をもっており、誰しもが悟りを開く可能性をもつ」という一乗思想を軸とした宗派です。釈迦の説いたさまざまな教えを総合的に学ぶことで、人々が仏の智慧(ちえ)と慈悲に近づき、現世と来世の安寧を得られるとされています。
ここでは、天台宗の主要な考え方や読まれる経典・お経について解説します。
顕教と密教
仏教には大きく分けて、釈迦の教えを経典の言葉から学ぶ「顕教(けんぎょう)」と、言葉では表せない修法を通じて仏の真理に近づこうとする「密教(みっきょう)」の2つの流れがあります。
顕教は主に経典を中心とした教えを説くのに対し、密教は真言(しんごん)や印契(いんげい)といった言葉だけでは表現できない宇宙の真理を追求し、生きながら仏となる道を重視するのが特徴です。
天台宗は、この顕教と密教の両面をあわせ持つ宗派として知られており、経典を読誦(どくじゅ)する法要だけでなく、加持祈祷などの密教法要を行う点が独自性とされています。
顕教法要
天台宗では、顕教法要として朝夕に読経が行われます。とくに法華経を唱え現世の罪を懺悔する「法華懺法」や、阿弥陀経を唱え極楽浄土への往生を祈る「例時作法」が代表的な儀礼です。
密教法要
密教法要としては、僧侶が真言や印契を組み合わせて、仏の威光を呼び起こし、故人の成仏を祈る儀式が行われています。
このように天台宗は顕教と密教の両面を併せ持っており、その特徴は葬儀などの儀式にも反映されています。
天台宗で唱えらえる経典・お経
天台宗は、法華経をはじめ複数の経典を重視しています。代表的なものとしては下記の3つが挙げられます。
法華経
天台宗の根幹をなす経典で、法要や修行の中心に位置づけられています。正式名称は「妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)」です。天台宗の軸となる「一乗思想」が説かれており「人はみな仏性をもっており、誰しもが仏となる可能性をもつ」という平等性を強く打ち出しています。
阿弥陀経
阿弥陀仏が住む極楽浄土を説いた経典である「阿弥陀経」は、浄土宗や浄土真宗でも読まれています。正式名称は「仏説阿弥陀経(ぶっせつあみだきょう)」です。
天台宗でも、往生や来世における浄土への希望を説く教えとして重要視されており、法華経とあわせて読誦されます。
般若心経
多くの宗派で唱えられる「般若心経」は、わずか260字ほどの短い経文でありながら、仏教の重要な教えである「空(くう)の思想」を説いた経典です。
正式名称は「般若波羅蜜多心経(はんにゃはらみったしんぎょう)」といい、天台宗の法要でも唱えられています。
「色即是空(しきそくぜくう)」「空即是色(くうそくぜしき)」という有名なフレーズに象徴されるように、物事の実相を見極め、執着から解放されることの大切さを教えています。
3.代表的な天台宗の葬儀の流れ
天台宗の葬儀は、他の仏教宗派と同様に通夜と葬儀が執り行われます。仏弟子としての資格を与える剃度式(ていどしき)や、法華経・阿弥陀経の読誦(どくじゅ)など、天台宗特有の儀式が含まれているのが特徴です。
通夜
通夜は、故人と最後の夜をともにしながら、遺族や参列者が焼香などを行い供養する大切な時間です。天台宗の場合、剃度式(ていどしき)などの独特な儀式が行われる場合があります。
臨終誦経(りんじゅうじゅきょう)
臨終誦経は、本来は臨終を迎える際に僧侶が枕元で阿弥陀経を読誦して、故人が極楽浄土へ往生できるよう祈るものでした。現在では、ご逝去後に行われるケースが多く、ご遺体の近くに経机を用意して僧侶が読経を行います。
通夜誦経(つやじゅきょう)
通夜の法要として、僧侶が朝と夕に経典を読み上げ、遺族や参列者が焼香を行います。天台宗の通夜では、朝は法華経、夕方は阿弥陀経を唱えるのが一般的です。
剃度式(ていどしき)
剃度式は、故人を出家した僧侶として送り出すための儀式です。本来は頭髪を剃る儀式ですが、現在では髪に剃刀を当てることで剃髪を表現するのが一般的です。
その後、香を焚いて故人を清め、戒名(かいみょう)を授けます。剃度式によって現世の煩悩を断ち、戒名を授けて仏の世界へ旅立つ準備が整うと考えられています。
葬儀
通夜を終えたあとに執り行われる葬儀は、故人を仏の世界へ送り出すための正式な儀式です。ここでは、天台宗の葬儀によく見られる式次第を紹介します。
導師・衆僧入堂
参列者が着席したのち、僧侶が入堂して葬儀が始まります。
列讃(れっさん)
開式の言葉が述べられたあと、天台宗独特の楽曲や声明(しょうみょう)を背景に、故人の最期を悼む唱和が行われます。シンバルに似た法具を打ち鳴らしながら歌う場合もあり、荘厳な音色とともに故人を偲びます。
光明供修法(こうみょうくしゅほう)
読経や合掌を通じて阿弥陀仏の光明を招き入れ、故人が仏として生まれ変わるよう願う儀式です。
九条錫杖(くじょうしゃくじょう)
錫杖(しゃくじょう)という法具を用いて、故人の功徳(くどく)を称えながら、僧侶と参列者が唱和する儀式です。錫杖は先端に複数の輪がついた杖のことで、歩くと輪が触れ合って音を立てるため、仏の教えを広めるシンボルとされています。
随行回向(ずいこうえこう)
僧侶が声明をあげながら、故人の成仏と参列者の供養の心を回向(えこう)する儀式です。読経によって故人への祈りを捧げるとともに、遺族や参列者も焼香などの作法を通じて追悼の意を示します。
鎖龕(さがん)・起龕(きがん)
列讃が再度行われたのち、棺(ひつぎ)のふたを閉じる「鎖龕」、そして棺を起こして送り出す準備をする「起龕」が行われます。
奠湯(てんとう)・奠茶(てんちゃ)
棺を閉じたあとの故人へのお供えとして、湯や茶を仏前に供える儀式です。清らかな水や茶を捧げることで、故人を清め感謝を伝えるとされています。
引導(いんどう)
僧侶が故人の生前の功績や徳を讃え「菩薩戒偈(ぼさつかいげ)」を唱えることで、菩薩として生きる心構えを示します。その後「引導」によって故人が迷うことなく仏の世界へ至れるよう祈願します。
下炬(あこ)と参列者による焼香
僧侶がたいまつや線香を用いて火を示し「下炬文(あこぶん)」という言葉を読み上げながら仏の光明を象徴的に描きます。その後、僧侶の読経が続くなか、参列者は順番に焼香を行い、故人への感謝や祈りを捧げます。
弔辞拝受と弔電拝読
焼香が終わった後、弔辞や弔電を披露し、生前の故人の人柄や功績を改めて振り返ります。
法施(ほうせ)
引き続き僧侶が読経を行い、仏法の功徳を故人と参列者へ施します。
念仏または光明真言
「南無阿弥陀仏」や「光明真言」を声に出して唱え、故人の往生や参列者の心の安らぎを祈ります。
総回向(そうえこう)
僧侶が回向文を唱え、葬儀の本式は結びとなります。
導師退場・出棺
僧侶が退場し、遺族および参列者も席を立ちます。最後に棺が運び出され、遺族や参列者に見送られながら火葬場へ向かいます。
4.天台宗の葬儀に必要な道具
天台宗の葬儀では、一般的な仏式葬儀で用いられる道具に加えて、天台宗特有の仏具を用意します。必要な道具や仏具は寺院や葬儀社が準備してくれる場合もありますが、事前に確認しておくといいでしょう。
一般的な仏式葬儀で使う道具
祭壇(さいだん)
葬儀会場に設置される供養のための台で、遺影や位牌、供花を飾ります。
経机(きょうづくえ)
僧侶がお経を読み上げる際に、経典や数珠などを置く小机です。
骨壺(こつつぼ)
火葬後の遺骨を納める容器で、葬儀後、一定期間を経てお墓に納骨するのが一般的です。
香炉(こうろ)
香を焚くための器で、焼香を行う際に用います。
遺影
故人の写真を入れて祭壇に飾り、参列者が故人の姿を偲ぶものです。
天台宗特有の仏具
木魚(もくぎょ)と木魚倍(もくぎょばい)
読経のリズムを取る際に叩く法具です。
鉦吾(しょうご)
小型の鐘のような形をしており、木魚とあわせて鳴らします。
錫杖(しゃくじょう)
天台宗の葬儀では「九条錫杖」という故人の徳を讃える儀式で使用されます。
茶湯器(ちゃとうき)
故人へお茶や湯を供える「奠茶・奠湯」の儀式で使用します。
上記はあくまで代表的な道具や仏具の例です。実際には、寺院や地域の慣習により使用される品目や作法が異なる場合もあるため、葬儀社や僧侶に相談しながら準備を進めましょう。
5.天台宗の葬儀の知っておくべきマナー・注意点
天台宗の葬儀に参列する際は、焼香や数珠、香典、お布施に関するマナーや注意点を理解しておくことが大切です。
焼香のマナー・注意点
天台宗では焼香の回数は3回が一般的ですが、厳密な決まりはありません。寺院や地域によっては1回の場合もあります。
焼香を行う際は、焼香台の前で軽く一礼したあと、右手の親指、人差し指、中指の3本で香をつまみ、額に掲げてから香炉にくべます。香をつまんだ手を額に掲げる「押し」の動作はあってもなくてもマナー違反にはなりません。焼香後は再度合掌し、一歩下がって再度一礼を行いましょう。
数珠のマナー・注意点
天台宗の正式数珠は、平玉を中心に108個の主玉が二重になった独特の形が特徴です。男性は9寸、女性は8寸が一般的で、僧侶は「大平天台」を持ちます。
親玉や天玉、弟子玉などを組み合わせることで煩悩を祓う意味があり、合掌時は親玉を上にして左手にかけ、両手で包むようにして持ちます。
香典のマナー・注意点
天台宗の葬儀では、香典の表書きに「御霊前」や「御香典」を用いるのが一般的です。四十九日以前は「御霊前」、過ぎてからは「御仏前」とする場合もあります。
金額は知人で3,000円〜5,000円、親族で1万円〜3万円、両親や義両親の場合は10万円ほどが目安です。
新札は避け、一度折り曲げるなどの配慮をしましょう。金額に応じて水引の有無や適切なデザインの香典袋を選び、受付では表書きが相手に読める向きに渡すのがマナーです。
お布施のマナー・注意点
お布施は、葬儀や法要を執り行っていただいた僧侶に対する謝礼ではなく「仏の教えをいただく感謝の気持ち」を形にしたものです。金額や渡し方など、他宗派の場合と共通する部分もありますが、戒名のランクとあわせて確認しておくといいでしょう。
お布施は、正式には半紙で包んだお札を「奉書紙」という和紙で包みます。奉書紙がない場合は、郵便番号の枠などの記載のない無地の白封筒に「御布施」と表書きしたもの、またはあらかじめ「御布施」と書かれた専用の封筒を使用しましょう。不祝儀袋は使わない点に注意してください。
表書きは「御布施」と書かれた下に施主の氏名を記載します。裏面には金額と施主の住所を記載しましょう。お渡しする際は、袱紗に包んで切手盆に乗せます。
お布施の相場は葬儀で20万〜35万円、戒名を授かる場合は30万〜100万円ほどが目安ですが、戒名のランクによっても異なります。
院居士・院大姉:100万円以上
院信士・院信女:50万円~100万円
居士・大姉:50万円~80万円
信士・信女:20万円~50万円
上記の価格は、あくまで一般的な目安となります。僧侶の交通費などは「御車代」「御膳料」として別途お包みする場合もあります。
なお、寺院や地域によってお布施の相場は異なる場合もあるため、事前に葬儀社と相談しておくといいでしょう。
6.天台宗の教えを知り、葬儀の流れやマナーを把握しておきましょう
天台宗は、法華経を中心とする一乗思想を軸に、中国伝来の密教を取り入れ、顕教と密教の両面をあわせ持つ仏教宗派です。奈良時代の僧である最澄が、比叡山延暦寺を拠点にその教えを広めました。
天台宗の通夜・葬儀では、剃度式や九条錫杖、奠湯・奠茶など独特の儀式が行われ、故人を仏の世界へ導きます。地域や寺院によって内容が異なる場合もあるため、あらかじめ確認をしながら準備を進めることが望ましいでしょう。
この記事を通じて、天台宗の葬儀の流れやマナーを理解し、大切な方を心を込めてお見送りする準備を整えてください。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。