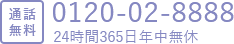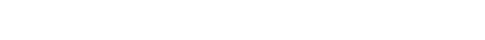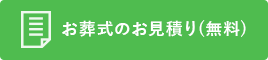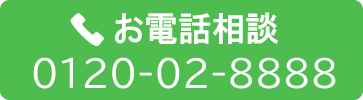「香典」について徹底解説!正しい表書きの書き方、香典袋の包み方、金額相場など総合的にご紹介します。
公開日:2025/01/17
更新日:2025/01/17

● 香典の金額相場について知りたい方
● 香典を包む際のマナーを確認したい方
● 香典を辞退された場合の対応にお悩みの方
1.香典とは?
「香典(こうでん)」とは、仏式の葬儀において、故人の霊前にお供えする金銭や物品のことをいいます。香典の「香」の字は、もともとは弔問客がお線香やお花などを持参してご霊前にお供えしていたことに由来しますが、時代の変化とともに、お線香やお花の代わりに現金を包んで持参することが一般的になりました。現在は、香典が葬儀費用の一部に充てられることも多く、ご遺族を経済的に助けるという意味合いも持っています。なお、「香」の由来である線香は仏教に関わるものであることから、「香典」という言葉は仏式葬儀にのみ使用されます。
2.お包みする香典の相場
葬儀や法要に参列する際、香典をいくら包むべきか頭を悩ませてしまう方も少なくないでしょう。香典の金額に決まりはなく、故人との関係性や地域性、ご自身の年齢や社会的な立場などによっても変わります。判断に迷う場合は、ご友人、ご親戚など、同じ立場で参列する方と相談し、金額を合わせても良いでしょう。以下に、故人との関係性別にみた香典の相場をご紹介しますが、あくまでも一般的な目安として参考にされてください。
■ 葬儀の香典
【親族】※配偶者の親族の場合も同様
| 故人との関係性 | 金額相場 |
|---|---|
| 両親 | 5〜10万円 |
| 兄弟・姉妹 | 3〜5万円 |
| 祖父母 | 3〜5万円 |
| おじ・おば | 1〜3万円 |
| その他の親戚 | 5千〜3万円 |
【友人・知人】
| 故人との関係性 | 金額相場 |
|---|---|
| 友人・知人 | 5千〜1万円 |
| 友人・知人の家族 | 3千〜1万円 |
| 近所の方など | 3千〜1万円 |
【職場関係者】
| 故人との関係性 | 金額相場 |
|---|---|
| 上司 | 5千〜1万円 |
| 同僚 | 5千〜1万円 |
| 上司・同僚の家族 | 3千〜1万円 |
■ 一周忌法要の香典
【親族】※配偶者の親族の場合も同様
| 故人との関係性 | 金額相場 |
|---|---|
| 両親 | 1〜5万円 |
| 兄弟・姉妹 | 1〜5万円 |
| 祖父母 | 5千〜3万円 |
| おじ・おば | 5千〜1万円 |
■ 香典の額面について
香典を包む際は、金額の数字にも配慮が必要です。一般的には、3千円、5千円、1万円、3万円といった「奇数」にしたほうが良いとされています。なぜなら、2万円などの「偶数」は割り切れる数字であるため、「縁が切れる」、「関係を割り切る」といったマイナスのイメージを与えかねないからです。また、2は「ふたたび」、「たびたび」といった不幸の繰り返しを、4は「死」、9は「苦」を連想する方もいらっしゃるため、香典では避けたほうが無難といえます。気にしない方もいらっしゃるかとは思いますが、大切な方を亡くして悲しみの最中にあるご遺族の気持ちにできるだけ配慮したいものです。
3.不祝儀袋の選び方
香典を包む際に使う不祝儀袋は、宗教・宗派に合わせ、包む金額にふさわしいものを選ぶ必要があります。たとえば、蓮の花がデザインされたものは仏教用であり、他の宗教では使用しません。同様に、ユリの花や十字架がプリントされたものはキリスト教用なので注意しましょう。また、包む金額が高額になるほど上質な素材で格式あるデザインのものを選ぶと、中身とのバランスがとれて違和感がありません。
香典で使われる水引の種類は、「あわじ結び」または「結び切り」です。いずれも簡単にほどけにくい結び方であり、「不幸を繰り返さない」という意味が込められています。以下の表に、不祝儀袋の選び方の目安をまとめました。
| 金額 | 水引の種類 | 水引の色 |
|---|---|---|
| 5千円まで | 印刷 | 黒白 |
| 1~3万円 | 水引あり | 黒白 |
| 3~5万円 | 水引あり | 黒白または双銀 |
| 5万円以上 | 水引あり | 双銀 |
4.香典袋の書き方
香典袋には、水引のついた外袋と、お札を入れる中袋が付いていることが一般的です。香典袋に書く文字のことを「表書き」といい、外包みには表書きと名前、中包みには金額や住所などを自分で書き入れる必要があります。書き方にはルールがあり、葬儀の宗教・宗派などによっても異なりますが、事前に大まかな内容だけでも把握しておくと良いでしょう。ここでは、香典袋の書き方について解説します。
■ 外袋の書き方
外袋の表面は、上段に「表書き」、下段に名前を書きます。表書きとは、香典を贈る名目のことで、葬儀の宗教・宗派に合わせることがマナーです。
【仏教の場合】
仏式の通夜・葬儀では、表書きを「御霊前(ごれいぜん)」と書きます。その後、四十九日以降は「御仏前(ごぶつぜん)」とすることに注意が必要です。ただし、浄土真宗では故人は亡くなってすぐに成仏すると考えられていることから、「御霊前」という表書きは失礼にあたり、通夜・葬儀の段階から「御仏前」とします。仏式葬儀でも宗派まで分からない場合は、「御香典(おこうでん)」としておくと間違いがないでしょう。
【神道の場合】
神式葬儀では、「玉串料(たまぐしりょう)」または「御榊料(おさかきりょう)」、「御神前(ごしんぜん)」などとします。多くの宗教・宗派に共通で使える、「御霊前」を用いても問題ありません。
【キリスト教の場合】
カトリック、プロテスタントともに「御花料(おはなりょう)」とすることが一般的です。「御霊前」は、プロテスタントではマナー違反にあたる場合もあるため避けたほうが良いでしょう。
【無宗教または宗教・宗派が分からない場合】
近年増えつつある無宗教での葬儀や宗教・宗派が不明の場合は、「御霊前」とすることが一般的です。「御香典」や「御花料」としても良いでしょう。
■ 名前の書き方
香典袋の表面に名前を書くとき、個人の場合は中央にフルネームを書くことが基本ですが、夫婦や会社の部署など連名で出す場合は、名前を書く順番や位置などにも注意が必要です。以下、ケース別に表にまとめましたので、お役立ていただければ幸いです。
| 人数 | 名前の書き方 | 位置 |
|---|---|---|
| 1人(個人) | 本人のフルネーム | 中央 |
| 2人(夫婦) | 夫のフルネーム +妻の名前のみ |
中央に夫の氏名 左に妻の名前 |
| 3人まで(連名) | 全員のフルネーム (会社・団体名がある場合は右に) |
中央から左へ目上→目下の順 ※上下関係がなければ五十音順 |
| 4人以上(連名) | 代表者のフルネーム +「他一同」または「他〇名」 (会社・団体名がある場合は右に) |
中央に代表者の名前、 左下に「外一同」・「外◯名」 ※白無地の便箋に全員の名前・ 住所・金額を記載して同封する |
| 会社・団体 | 会社・団体代表者の フルネーム |
中央に代表者名、 右側に会社・団体の名称 |
■ 中袋の書き方
お札を入れる中袋には、表に金額を、裏に住所と氏名を記入します。後日、ご遺族が中袋に書いてある情報をもとに香典返しや礼状などを手配することがあるため、住所や氏名は省略せず正しく書きましょう。
金額は、改ざんや読み間違いを防ぐという目的から、旧字体の漢数字を用います。たとえば、5千円を包む場合は「金伍仟圓也」、1万円なら「金壱萬圓也」、3万円の場合は「金参萬圓也」、10万円は「金拾萬圓也」と書きます。「圓」は「円」の旧字体ですが、圓と円どちらを用いても問題ありません。
■ 筆記用具について
香典は、薄墨の毛筆、または筆ペンを使って書くことが基本です。薄墨を用いる理由は、「落とした涙で墨がにじんでしまった」、「悲しみのため墨をする力さえもない」など、故人を悼む気持ちを表現するためといわれています。薄墨の筆ペンを用意できない場合は、黒色のサインペンを用いても失礼にはあたりません。葬儀は突然起こる出来事であり、用意をする時間がない場合はやむを得ないと考えられているためです。だからといって、ボールペンや鉛筆で代用することはマナーに反するため避けましょう。
また、最近は弔事用のスタンプなども市販されており、利用すること自体はマナー違反にあたりませんが、中には簡略化するのは失礼だと考える方もいらっしゃいます。できるだけ手書きを選択するほうが、故人の死を悼み、ご遺族の心情に寄り添う気持ちが、より伝わりやすくなるのではないでしょうか。
5.香典をお渡しするときの注意点・マナー
ここでは、香典をお渡しするにあたって注意したい点やマナーについて、お金の包み方から、持参するときや実際にお渡しする際の作法まで詳しくご紹介します。
【新札は使わない】
結婚式などの慶事では新札を包むことがマナーとされていますが、香典の場合は逆に新札は避けるべきものとされています。これは、「不幸に対してあらかじめ準備をしていた」と思われないためのマナーです。香典には、新札を使わず、しわの入った古札を用いましょう。とはいえ、あまりにもしわの多いものや汚れたもの、破れたものを使用することはご遺族に対して失礼にあたります。受け取る側の気持ちを考えて、ある程度使用感はあっても綺麗な古札を選ぶことが大切です。
新札しか手元になく古札を用意することが難しい場合は、新札に一度折り目をつけて包めば問題ありません。このときも、たくさん折り目をつける必要はなく、真ん中から二つに折るだけで十分です。
【お札の向きに注意】
お金を入れるときは、お札の向きにも注意が必要です。袋の「表面」に対して、お札が「裏面(肖像画が印刷されていない面)」を向くようにお金を入れましょう。肖像画を裏向きにすることには、「顔を伏せて故人の死を悼む」という意味が込められています。上下の向きについては、お金を取り出したときに肖像画が見えないよう、袋の下部に肖像画が位置する向きで入れましょう。
【外袋は上側を重ねる】
外袋は、先に下側を上に折ってから、上側を下に折ってかぶせるのが不祝儀の折り方です。上側を重ねて、「不幸や悲しみを上から下へ流す」と考えると覚えやすいかもしれません。慶事の場合とは折り方が逆になるので、十分に気をつけましょう。
【持参する時は袱紗(ふくさ)を使用】
香典袋は、そのままバッグなどに入れるのではなく「袱紗(ふくさ)」に包んで持参します。袱紗とは、不祝儀袋が汚れたり型崩れしたりすることを防ぎ、綺麗な状態でご遺族にお渡しするためのものです。袱紗は、デパートやショッピングセンターなどの礼服売り場、スーツ専門店、仏具店、書店などの文具コーナーの他、コンビニエンスストアや100円ショップなどで購入することが可能です。弔事で用いる袱紗は、紫色、藍色、グレーといった暗い寒色系のカラーを選びましょう。赤、朱色、オレンジ、ピンクなど、明るい暖色系のものは慶事用なので香典にはふさわしくありません。紫色は、弔事と慶事のどちらにも使うことができるので初めて袱紗を購入する方にお勧めです。袱紗を使う機会は年齢を重ねるにつれて増えていくことが多いので、一つ用意しておくと安心でしょう。
【香典をお渡しするタイミング】
香典は、通夜や葬儀・告別式で渡すことが一般的です。通夜と葬儀・告別式の両方に出席する場合は、そのいずれかでお渡ししますが、一般的には通夜でお渡しする方が多いようです。通夜と葬儀・告別式の両方で香典を包むのは、マナー違反になるので気をつけましょう。弔事において、同じ行動を繰り返すことは「不幸が重なる」という意味につながるためです。
【香典の渡し方】
香典をお渡しする際にもいくつかのマナーがあります。当日失礼のないよう事前に確認しておきましょう。
●相手から表書きが見えるように渡す
受付で記帳を済ませた後、袱紗から香典を取り出します。受付にあるお盆や台の上に置き、お渡しする方の目の前で、相手から見て表書きが読めるよう反時計回りに回転させて香典の向きを変えます。お盆などがない場合は、たたんだ袱紗の上に重ねて代用しましょう。そして、必ず両手で香典をお渡しします。
●お悔やみの言葉を添える
香典をお渡しするときは、お悔やみの言葉を述べると丁寧です。「このたびは誠にご愁傷さまでございます」、「心よりお悔やみ申し上げます」など簡潔にお悔やみを述べ、「どうぞ御霊前にお供えください」と一言添えて香典をお渡しします。このときに、「忌み言葉」を使わないように気をつけましょう。忌み言葉とは、「切る」、「消える」、「終わる」、「落ちる」といった、不幸を連想するような縁起が悪いとされる言葉のことです。忌み言葉には、「ますます」、「くれぐれも」、「いろいろ」など、同じ単語を繰り返すことで不幸が再び起きることを連想させる「重ね言葉」も含まれます。日常的な会話で使うことも多い単語も含まれているため、あらかじめ確認し、当日うっかり口にしてしまわないよう注意しましょう。
6.葬儀に参列しないときの香典の渡し方
様々な事情で通夜や葬儀・告別式への参列が難しいものの、香典をお渡しすることで弔意を示したいという場合があるかもしれません。そのようなときは、代理の方に参列をお願いする他、後日弔問に伺う、香典を郵送する、といった方法があります。
■ 代理人に託す場合
ご自身が参列することが難しい場合は、代理の人にお願いしても失礼にはあたりません。その場合はご遺族に電話などで連絡し、代理人に香典を託す旨を事前に伝えておくことが重要です。お金にかかわることであるため、マナーとしても、トラブルを避ける意味でも、忘れずに連絡を入れましょう。
香典袋には依頼主の名前を書き、左下に小さく「代」、または依頼主の配偶者が代理人となる場合は「内」と記載します。これは、代理人を立てたことを受付の人やご遺族にわかりやすくするためです。
■ 後日弔問する場合
お通夜や葬儀・告別式に参列できない場合は、後日ご自宅へ弔問して香典を直接お渡しするという方法もあります。弔問するときは、あらかじめご遺族に連絡を入れ、先方の都合のよい日時に伺いましょう。葬儀直後は、慌ただしく心身ともに落ち着かない時期なので避けたほうが無難です。葬儀後3〜4日経ってから、四十九日法要くらいまでの間に訪問すると良いでしょう。
■ 香典を郵送する場合
香典を手渡しできない場合は、郵送することも可能です。参列できないことが分かったら、できるだけ早い段階で送りましょう。当日に間に合うようであれば、日付指定をして通夜・葬儀が行われる会場へ直接郵送して問題ありません。葬儀が終わってから送る場合は、葬儀直後を避け、葬儀後1週間〜遅くとも1カ月以内には届くよう喪主宛に郵送します。ご遺族は香典返しを用意する必要がありますので、あまり時期が遅くならないよう心がけましょう。
郵送する際は、現金を香典袋に包み、現金書留で郵便局の窓口から発送します。普通郵便では現金を送ることはできません。郵送の場合も、不祝儀袋の書き方や包み方、お金の入れ方などのマナーは手渡しと同様です。現金書留の専用封筒に必要事項を記入するからといって、住所や氏名、金額などの記入を省略してはいけません。
また、香典にはお悔やみの手紙を同封しましょう。お悔やみの手紙では、時候の挨拶や「拝啓・敬具」といった頭語・結語は省略します。手紙には、故人に対するお悔やみに加え、葬儀・告別式に参列できないことへのお詫び、香典を郵送すること、ご遺族に対する心遣いや故人の冥福を祈る言葉を書きます。口頭でお悔やみを述べる場合と同じく、手紙の文中でも忌み言葉を使わないよう注意が必要です。
7.香典を辞退されたときは?
近年は葬儀形式も多様化しており、少人数の身内だけで行う「家族葬」など、ご遺族が香典を辞退するケースも増加傾向にあります。その背景には、参列者に負担をかけたくないという気遣いはもちろん、香典返しなどご遺族自身の負担を軽減したいという気持ちが込められていることも少なくありません。
香典を辞退する旨の連絡があった場合は、ご遺族の意向を尊重し、香典を持参しないのがマナーです。無理にお渡しすることは、ご遺族の負担になりますので避けましょう。それでも、何らかの形で弔意を示したい場合は、香典の代わりにお供物や供花、弔電をお贈りするのも一つの方法です。ただし、香典だけではなくお供物や供花も辞退している場合がありますので、必ず事前にご遺族へ確認をとり、弔意からの行動がかえってご迷惑にならないよう気をつけましょう。
8.香典についての要点まとめ
●「香典」とは、仏式葬儀において故人の霊前にお供えする金銭や物品のこと。
・もともとは弔問客が線香やお花を供えたことに由来するが、現代では現金を包むのが一般的
・線香は仏教に関わるものであることから、仏式以外の葬儀では「香典」という言葉は用いない
●香典の相場は、故人との関係性や地域性、参列者本人の年齢などによって異なる。
・判断が難しい場合は、同じ立場で参列する人と相談して金額を決めるのも一つの方法
・香典の金額は、割り切れる「偶数」や縁起が悪いとされる数字は避けたほうが望ましい
●香典袋は、葬儀の宗教・宗派に適したもの、包む金額に見合ったものを選ぶ。
・香典袋の書き方にはルールがあり、宗教・宗派ごとに「表書き」が異なる点に注意
・お金を包む際も、新札は使わない、お札を裏向きに入れるなど、マナーに気をつける
●香典は通夜か葬儀・告別式のいずれかで渡し、複数回渡すのはマナーに反する。
・袱紗に香典を包んで持参し、相手から表書きが見えるように両手で持ってお渡しする
・香典を渡す際はお悔やみの言葉を述べる。その際、忌み言葉を使わないように注意
・参列できない場合は、代理人に託す、後日弔問する、香典を郵送するといった方法も
・香典を辞退された場合は持参しない。お供物や供花を送る場合も遺族に確認が必要
メモリアルアートの大野屋では、お葬式やお仏壇、お墓のことから、仏事のマナーやお盆など季節の仏事のしきたりにいたるまで、 専門の相談員が年中無休、無料でご相談にお答えしています。御香典の包み方などお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。