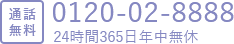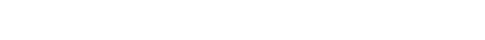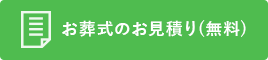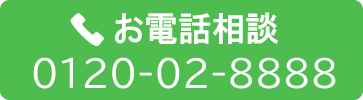病院での死亡後、遺族がやるべきことは?納棺までの流れを解説
公開日:2025/01/28
更新日:2025/01/28

病院で大切なご家族が亡くなった際は、深い悲しみに暮れると同時に、短い時間のなかでやるべきことが次々と発生します。死亡診断書の受け取りや退院の手続き、葬儀社への連絡など、やるべきことの流れを把握していないと、戸惑いや負担がさらに大きくなるかもしれません。
そこで本記事では、病院で逝去した際に遺族がまず行うべきことや、納棺に至るまでの具体的な流れをわかりやすく解説します。親族への訃報連絡のタイミングや葬儀社の役割、退院後の流れなども詳しくご紹介しています。突然の事態に落ち着いて対処するための参考になれば幸いです。
● 病院で死亡した場合の手続きや流れを知りたい人
● 親族への訃報連絡のタイミングについて知りたい人
● 病院で死亡した場合の葬儀社の役割を知りたい人
● 病院で死亡した場合の退院後の流れを知りたい人
1.現代は病院での死亡・ご逝去が約7割
現代では、病院で亡くなる方が、約7割にのぼるといわれています。遺族は深い悲しみのなか、短時間で葬儀準備や手続きを進めなければなりません。
死亡確認後は、死亡診断書の受け取りや葬儀の準備、退院手続きなどが同時に進行し、慌ただしくなることも少なくありません。突然の事態に落ち着いて対処するためにも、病院で亡くなった場合にやるべきことや手続きの流れをあらかじめ理解しておくことが大切です。
2.逝去後に病院で行う手続きと流れ
病院でご家族が亡くなられた場合、まずは医師による死亡確認から始まり、短時間のうちに複数の手続きが進められます。
病院ごとに流れが異なることもありますが、一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
医師による死亡確認
遺族による末期の水(まつごのみず)の儀式
看護師によるエンゼルケアの実施
搬送先(安置場所)の手配
死亡診断書の受け取り
退院の手続き
1つずつ詳しく見ていきましょう。
1.医師による死亡確認
病院で臨終を迎えた場合、医師が「死の3徴候」などを確認し、死亡時刻を正式に判断します。
<死の3徴候>
心拍停止
呼吸停止
瞳孔の散大と対光反射の消失
法律上、死亡の確認は医師のみが行うことができ、確認後は医師からご逝去の事実と時刻が遺族に伝えられるのが一般的です。
2.遺族による末期の水(まつごのみず)の儀式
医師の死亡確認後、遺族が故人の口元を水でうるおす「末期の水(まつごのみず)」という儀式を行うことがあります。宗派や地域によって方法は異なりますが、水を含ませた脱脂綿などを使って口元を湿らせるのが一般的です。
この儀式には「生前に受けた苦しみや煩悩を洗い流し、安らかな旅立ちを祈る」という意味合いが込められており、最後の別れを大切にする気持ちが表されています。
3.看護師によるエンゼルケアの実施
末期の水の儀式が終わると、看護師など医療スタッフが故人の身体を清め、死装束への着替えや死に化粧を施すといった「エンゼルケア」を行います。エンゼルケアの所要時間は、30分〜1時間程度が一般的で、病院によっては専門のスタッフが在籍している場合もあります。
エンゼルケアを行い、故人をきれいな姿で見送りすることは、故人の人格や尊厳を守るとともに、遺族の心のケアにもつながります。
4.搬送先(安置場所)の手配
亡くなられた方のご遺体は、エンゼルケアによる処置後、病室から霊安室へ移動されるのが一般的です。しかし、霊安室での保管は2〜3時間前後と限られているため、できるだけ速やかに退院後の搬送先(安置場所)を決める必要があります。
安置場所には、自宅や葬儀社や斎場の安置室、民間業者の安置室などの選択肢があります。安置場所を決定する際は、葬儀社にも相談しながら、ご遺族や親族が集まりやすい場所を選ぶといいでしょう。
霊安室と安置室の違い
霊安室は病院に設けられた一時的な保管場所です。亡くなられた方のご遺体を安置場所へ搬送するまでの短期間だけ利用でき、長期の安置はできません。
一方、安置室は葬儀社や斎場などの施設内に設置されており、火葬や葬儀までのあいだ故人をゆっくり弔うために必要な設備が整っています。遺族や親族が面会に訪れ、静かな時間を過ごせるのも安置室の特徴です。
5.死亡診断書の受け取り
医師の判断をもとに「死亡診断書」が作成されます。死亡診断書は、葬儀などを進めるために欠かせないものなので、ご遺族は忘れずに受け取りましょう。
死亡診断書を添えて市区町村役所へ「死亡届」を提出すると、火葬や埋葬に必要な「火葬許可証」が発行されます。提出期限は「死亡の事実を知った日から7日以内」が原則です。
6.退院の手続き
死亡診断書を受け取ったら、病院側で退院の手続きが行われます。費用の支払いは後日行うケースが多いため、退院手続きの際に支払方法についてよく確認しておきましょう。
また、退院手続きと同時に葬儀社へ連絡して、遺体搬送車を手配してもらうのが一般的です。遺体搬送の料金は数万円が目安となります。例えば10kmまでは15,000円前後、それ以降は一定距離ごとに加算されるなどのケースが多いですが、地域によっても異なるため事前に確認しておくと安心です。
法律的には、自家用車でご遺体を搬送することも可能ですが、ご遺体搬送には専門的な知識や設備が必要になります。また、搬送中にご遺体を傷つけてしまったり、目的地とは異なる場所へ行ってしまうと、法に触れる可能性もあります。そのため、葬儀社に依頼することをおすすめします。
3.親族への訃報連絡はいつする?
危篤の状態が続いている場合は、身内や最期に立ち会わせたい方に早めに連絡をしておきましょう。
危篤から持ち直すこともあるため、連絡のタイミングを図るのが難しいと感じるかもしれません。しかし、ご家族の最期の時間となる可能性もあるため、大切な方には早めに連絡するのが望ましいです。
医師が「臨終」と判断したあとは、葬儀の日取りや場所が決まっていなくても、まずは「亡くなった」という事実を親族や大切な方へ伝えるようにしましょう。連絡の際には「お通夜や葬儀の日時・場所は追って連絡する」といったひと言を添えると、相手も段取りしやすくなります。
また、近しい人々へ連絡する際に抜け漏れがないよう、事前に連絡先をリストアップしておくといいでしょう。いざというときに慌てずに対応するためにも、下記の関連記事で、訃報連絡の文例や注意点を確認しておくこともおすすめします。
関連記事:
知っておきたい訃報の連絡:文例を添えたケーススタディ
余命宣告をされたら?心構えややるべきこと、準備や手続きなどを解説
家族が危篤状態になったときの対応ガイド 〜心の準備と大切なポイント〜
4.病院で逝去した場合の葬儀社の役割
病院でご家族が亡くなった場合、まず必要になるのがご遺体の搬送です。病院の霊安室は長時間の安置を想定していないため、ご遺体を自宅などの安置場所に移す必要があります。この搬送を請け負うのが、葬儀社の大きな役割です。
多くの場合、短時間のうちに搬送先を決定する必要があるため、事前に葬儀社の連絡先を用意しておくとスムーズに手続きできるでしょう。
病院から葬儀社を紹介される場合もありますが、必ずその葬儀社に依頼しなければならないわけではありません。すでに信頼できる葬儀社があるなら、そちらに頼む方法もあります。
また、搬送と葬儀の依頼先を別々にすることも可能です。たとえば、退院後の搬送は病院紹介の葬儀社に依頼し、葬儀は別の葬儀社にお願いするケースもあります。その場合は、搬送を依頼する葬儀社に「搬送のみ」と明確に伝えましょう。
こうした柔軟な選択肢を知っておくと、ご遺族が納得できるかたちで大切な人を送り出す準備を進めやすくなります。事前に故人の希望を含めた情報を整理しておけば、いざというときの負担を軽減できるでしょう。
5.退院後の流れ
退院後はご自宅などにご遺体を安置し、葬儀の日程や会場の調整を行いながら、葬儀当日に向けた準備を進めます。ここでは、主な流れとポイントを見ていきましょう。
ご遺体の安置と僧侶への連絡
病院からご遺体を搬送したあとは、自宅や斎場の安置室などに故人を安置します。菩提寺がある場合は、ご遺体の安置が整い次第、速やかに連絡をしましょう。その際、枕経(まくらぎょう)や枕勤めについても相談します。
ご遺体を安置する際は、枕飾り(まくらかざり)を用意するのが一般的です。枕飾りとは、故人を供養するためにご遺体の枕元に仏具やお供え物を飾る簡易的な祭壇のことです。枕飾りは、お通夜の準備が始まるまで安置場所に設置し、弔問客が線香を手向けたり祈りを捧げたりする場としての役割も果たします。
枕飾りは、宗派や地域によって準備するものや飾り方が異なるため、準備に関しては葬儀社に相談するといいでしょう。
葬儀社との打ち合わせ(会場・葬儀日程等)
ご遺体の安置が整ったら、葬儀を担当する葬儀社と会場の予約や日程調整、参列者の人数などを相談します。
葬儀のスタイル(一般葬・家族葬・直葬など)によって必要な物品や会場も変わるため、希望のかたちを担当者にしっかり伝え、見積もりを確認しながら準備を進めましょう。
親族・友人・知人への連絡
葬儀日程や会場が決まり次第、親族や故人の友人・知人へ連絡を行います。連絡の優先順位をあらかじめ決めておくと、混乱を避けやすくなります。連絡の際は、以下の項目を明確にして伝えましょう。
◆通夜、葬儀・告別式の日時
◆通夜、葬儀・告別式の会場
◆喪主
◆連絡先
連絡方法は電話やメールなど、相手との関係性や状況に応じて使い分けるのがおすすめです。また、近年はLINEなどのSNSを活用した連絡も一般的になってきています。
湯灌(ゆかん)の儀
湯灌(ゆかん)の儀とは、納棺前に故人の身体を湯水で洗い清める日本古来の儀式です。生前の苦しみや疲れを洗い流し、安らかに旅立ってほしいという思いが込められており、かつては家族が行っていました。
病院で亡くなった場合は、湯灌の儀は行わず、ガーゼや脱脂綿をアルコールに浸して全身を拭き清める「清拭(せいしき)」が行われるのが一般的です。しかし、希望があれば専門の湯灌師に依頼し、自宅や専門の設備が整った施設で、納棺前に湯灌の儀を行うことが可能です。
湯灌の儀では、浴槽での洗浄や洗髪、顔剃りを行い、白装束への着替えやヘアセット、化粧などを丁寧に施します。湯灌の儀を行うことで、遺族が故人と改めて向き合い、心の整理をするきっかけにもなります。ただし、依頼先によって費用や手順が異なるため、必ず見積もりを確認しておきましょう。
納棺
納棺は、葬儀社のスタッフが主となって行うケースが多いですが、遺族が参加できる場面もあるので、希望があれば事前に相談しておきましょう。棺に入れる副葬品(思い出の品や手紙など)を準備する際は、火葬できるもの・できないものを事前に確認しておくとスムーズです。
6.病院で亡くなった際の手続きややるべきこと、流れを把握しておきましょう
病院でご家族が亡くなると、短時間のうちに葬儀社や搬送先の手配を進める必要があり、深い悲しみの中で慌ただしく対応しなければならない場面が多く生じます。特に、病院の霊安室は長期安置を想定していないため、数時間以内に移動しなければならないケースも少なくありません。
こうした事態に備えるためには、あらかじめ依頼する葬儀社や搬送先を決めておくのがおすすめです。また、病院から紹介された葬儀社への依頼は必須ではなく、信頼できる葬儀社がある場合はそちらに任せることも可能です。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀や法要に関するお悩みに対応するベテランスタッフが常に待機しております。ご不明点やご質問があれば、いつでもお気軽にご相談ください。