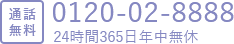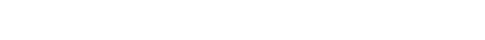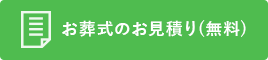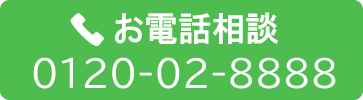生前葬はどんな葬儀?内容やメリット・デメリット、注意点を総合解説!
公開日:2025/02/13
更新日:2025/02/13

近年、ご自身が元気なうちに喪主となり執り行う「生前葬」が注目を集めています。人生の節目として前向きに検討される方も多い一方で、費用や準備の手間、周囲の反応など、気になる点が多いことも事実です。生前葬について、特徴や意義などを正しく把握しておくことで、こうした戸惑いや不安を軽減することができるでしょう。
そこで本記事では、生前葬の基本や費用相場、メリット・デメリット、具体的な流れや注意点を総合的に解説します。生前葬の特徴を理解し、ご自身やご家族に合った最適な選択を検討するうえでの参考にしてください。
● 生前葬の特徴や意義を知りたい人
● 生前葬と一日葬、家族葬の違いを知りたい人
● 生前葬の事前準備について知りたい人
● 生前葬の費用について知りたい人
● 生前葬の当日の流れを知りたい人
● 生前葬のメリット・デメリット、注意点について知りたい人
1.生前葬はどんな葬儀?
生前葬とは、一般的な葬儀のように「故人を見送る場」ではなく、本人が存命中に自ら喪主(主催者)となって行う葬儀のことです。
多くの場合、今までお世話になった方々を招待し、直接「ありがとう」を伝える場として活用されます。近年では有名人の実施がきっかけとなり、一般の方にも選択肢の1つとして徐々に認知が広がっています。
生前葬の特徴・意義
一般的な葬儀では、通夜・告別式・火葬など宗教儀式の流れを重視するケースが多いですが、生前葬では無宗教スタイルや趣味を反映した演出など、本人の希望や思い出を自由に盛り込める点が大きな特徴です。
また、式次第や演出内容も「明るく楽しくしたい」「ここまでお世話になった方々に感謝を伝えたい」といった、ポジティブで前向きな意図を反映するケースが多い傾向にあります。
通常の葬儀が「故人を見送る」という意味を持つのに対して、生前葬は「人生にひと区切りをつける」「お世話になった方へ感謝を伝える」といった意味合いが強くなります。そのため、服装やマナーについても平服参加や会費制を採用するなど、比較的自由度が高いのも特徴です。
生前葬を行う動機や理由
近年では、ライフステージの多様化に伴い「元気なうちに支えてくれた人へ感謝を伝えたい」「十分にお礼を伝えられないまま、亡くなりたくない」と考える方が増えています。
なかには定年退職や古希・喜寿などの年齢を迎え、人生の節目として「生前葬」を検討されるケースも少なくありません。
また、従来の葬儀は短い日数で準備をする必要があり、遺族の負担が大きくなる傾向があります。そのため、生前葬であらかじめ式を行っておき、死後の葬儀を縮小・簡略化しようと考える方もいます。
さらに、エンディングノートの作成などで「終活」が普及している今、最後のセレモニーを、自ら自分らしく企画したいと考える方が増えているのも事実です。
一日葬・家族葬との違い
本人が存命中に行う「生前葬」に対して、「一日葬」や「家族葬」という言葉は、亡くなったあとに行われる葬儀に対して使用されるのが一般的です。
一日葬は通夜を行わず、葬儀・告別式・火葬を1日で完結させる形式で、費用面や日程面での負担を抑えたい方が選ぶケースが多い葬儀形態です。
また、家族葬は親族や親しい友人のみで故人を見送る小規模な葬儀で、落ち着いた雰囲気の中、ゆっくりお別れができるというメリットがあります。
これらはいずれも「亡くなったあとに行われる葬儀」であるため、本人が元気なうちに主催・企画する生前葬とは根本的に異なります。
2.生前葬の事前準備
生前葬は、従来の葬儀とは違い「本人が生きているうちに主催する」ことが大きな特徴です。そのため、準備段階においても、通常のお葬式とは異なる手順を踏むことになります。
まずは、生前葬を扱っている葬儀社へ相談する
生前葬は通常の葬儀とは異なる進行や準備が必要となるため、生前葬の実績や対応プランが充実した葬儀社に依頼するとスムーズです。
費用面や式の演出、会場の選択肢など、具体的なイメージを葬儀社の担当者とすり合わせていきましょう。
会場や式次第を決定する
続いて、実際に生前葬を行う会場と式の流れを決めます。
近年では葬儀場やセレモニーホールだけでなく、ホテルやレストランなどを会場に選ぶケースも見られます。会場は、ご本人が希望する演出や雰囲気、招待予定人数に応じて、自由に検討可能です。
式次第(式の流れ)については、挨拶や映像演出、会食などを組み込むのが一般的です。一般的な葬儀とは異なり「明るい音楽を取り入れる」「趣味の品を飾る」など、本人らしさを演出するアイデアを盛り込むことで、生前葬ならではの個性を際立たせることができます。
招待客へ招待状を送付する
会場や式次第、日程が決まったら、招待客へ招待状を送付します。
開催日時や会場、服装の指定(平服で問題ないか、会費制を採用するかなど)を明記した招待状を送り「生前葬を行う想い」を一言添えておくと、参列を検討している方も安心して参加しやすくなるでしょう。
イメージ通りの納得した生前葬を実現するためには、綿密な事前準備が必要です。メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが生前葬の相談を承っております。
3.生前葬の費用について
生前葬の費用は、招待する人数や会場の種類、プランの内容などによって大きく変わります。
たとえば、数名~20名以下ほどの小規模な生前葬であれば、会場使用料や会食を含めて20万〜30万円程度に抑えられる場合があります。ただし、同じ小規模の式でも、演出内容や飲食のグレード、会場のランクを上げれば、30万円〜40万円を超えることも珍しくありません。
参加人数が30名〜50名前後になると、50万円〜70万円前後の費用が掛かるのが一般的です。高級ホテルなどで、大規模に華やかな会を行うのであれば、費用は150万円〜200万円を超えるケースも少なくありません。
生前葬は自由度が高いからこそ、どのような内容を重視するかによって必要となる予算が変わります。そのため、どの程度の規模や演出を希望するかをあらかじめ明確にして、複数の見積もりをとったうえで検討するのがおすすめです。
4.生前葬のメリット
生前葬は、本人が存命中に自ら喪主として式を主催するため、通常の葬儀にはないメリットがあります。ここでは、その代表的なメリットを3つ見ていきましょう。
本人からお世話になった人に直接感謝を伝えられる
生前葬の大きな利点は、本人が式に参加し、支えてくれた方々へ自分の言葉で「ありがとう」を伝えられることです。
一般的な葬儀では、故人が想いを直接表す機会はなく、家族が代弁する形になります。生前葬であれば普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちをしっかりと言葉にできるため、悔いを残しにくいのも特徴です。参列者との交流を通して、残される人だけでなく本人にとっても、大切な思い出となるでしょう。
自分で葬儀の内容を考えられる
生前葬は、宗教的な慣習や形式にとらわれず、自由度の高さが魅力です。本人の趣味や過去のエピソードを反映させる、映像で人生を振り返る演出を盛り込むなど、参加者も楽しめる多彩なアレンジを取り入れられます。
また、一般的な葬儀の場合は逝去直後の短時間で数多くの決定を迫られるため、どうしても慌ただしく式の内容を詰めることになりがちです。生前葬であれば、複数の葬儀社に相談したり、じっくりと打ち合わせの時間を確保したりしながら準備を進められるため、より納得のいく形で式を作り上げることができるでしょう。
家族への負担が軽減する
一般的な葬儀では、遺族が短い期間で多くの手配をこなさなくてはならず、精神的にも身体的にも大きな負担を抱えがちです。
生前葬なら、会場選びや費用の管理、進行の段取りなどの主要な準備を本人が主体的に行えるため、遺族の負担や迷いが軽減されます。
さらに、あらかじめ「どういう式にしたいのか」を明確にしておくことで、家族との意思疎通も円滑になり「想いのズレ」や「準備の行き違い」が生じにくい点もメリットです。
5.生前葬のデメリット
生前葬には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットがあることも理解しておくことが大切です。ここでは、検討段階で考慮しておきたい3つのデメリットをご紹介します。
二度手間になる場合がある
生前葬を行ったとしても、本人が亡くなったあとに改めて葬儀を行うケースがあります。
たとえば、家族や親族が「きちんと送り出したい」という思いから、亡くなったあとに一般的な葬儀を行うことも考えられます。こうしたケースでは、結果的に二度のセレモニーを実施することになり、費用や準備の手間が倍増してしまいます。
とくに、遺族の意向と本人の意志が食い違う場合は、事前の話し合いが欠かせません。
周囲の理解を得るのが難しいこともある
生前葬は一般的な葬儀に比べると、まだまだ認知度が低いのが現状です。そのため、親族や友人のなかには「生きているうちに葬儀をすることに違和感を覚える」という人もいるかもしれません。
また、宗教観や慣習の違いによっては「不謹慎だ」「理解できない」という反応を示されることもあるでしょう。
「生前葬を行いたい」という思いが周囲に受け入れられず、結果的にトラブルへ発展する可能性もあります。そのため、生前葬を希望する理由や意味などを含めて、事前に丁寧な説明を行い、周囲の理解を得ることが大切です。
自分本意な会になってしまうことも
生前葬は、本人の意志を最優先して計画できる反面、周りの人への配慮が不足してしまうと「自分だけが楽しむ場」になりかねません。
たとえば、ゲストが求める交流の場がまったく用意されていなかったり、本人の要望だけを詰め込みすぎてゲスト側の負担が大きくなったりすると、参列者に不満を与えてしまうかもしれません。
生前葬とはいえ、ゲストを招く「セレモニー」であることを意識し、あくまで感謝の気持ちを伝える場としてふさわしい内容を意識することが大切です。
6.一般的な生前葬の流れ
生前葬は、従来の葬儀と比べて形式に縛られず、重苦しい雰囲気を和らげる工夫が多く取り入れられています。儀式や宗教的な手順よりも、本人の人生や感謝の思いを伝える時間が中心になるため、自然と明るいムードになりやすいのが特徴です。
ここからは、生前葬の一般的な流れをご紹介します。
1.開式の言葉
司会者や進行役が開式を宣言し、参列者に向けて式の趣旨やプログラムを案内します。
2.主催者(本人)の挨拶
生前葬では、本人が喪主となります。そのため、挨拶と合わせて「なぜ生前葬を行うのか」「どのような思いで準備してきたのか」を自ら語るケースが多く見られます。
3.自分史の紹介
写真や映像を用いて、生まれてから現在に至るまでの人生を振り返ります。友人や家族にとっても、思い出を共有できる大切な時間です。
4.来賓の挨拶
主催者と深く関わりのある来賓(上司や恩師など)が挨拶を行う場面です。主催者への思いやエピソードが語られ、会場に温かい空気が広がるでしょう。
5.演奏や余興
宗教儀式にこだわらない生前葬だからこそ、明るい音楽の生演奏や趣味を生かした余興が取り入れられるケースもあります。
6.友人のスピーチ
親しい友人が登壇し、主催者との思い出や日頃の感謝をスピーチします。笑い話や懐かしいエピソードなどが飛び交い、会場を盛り上げることも少なくありません。
7.会食と歓談
生前葬は「集まってくれた人と直接語り合う場」としての意味合いが強い式です。そのため、食事をしながら歓談の時間をしっかりと設けるのが一般的です。本人がテーブルを回って、直接お礼を伝えるケースも見られます。
8.閉式の言葉
本人から改めての感謝の言葉が伝えられ、締めくくられるのが一般的です。
ここで紹介した流れは、一例です。生前葬では、本人が主体的に流れを決められるため、演出やプログラムは多彩です。従来の葬儀とは違い、心身ともにあまり堅苦しくならず、参列者も笑顔で参加しやすい流れにするといいでしょう。
メモリアルアートの大野屋では、ご自宅のリビングのようなくつろぎ空間で、静かに温かく見送るための家族葬専用施設「フューネラルリビング」もご用意しています。
フューネラルリビングでは、アットホームな生前葬の実施も可能です。
7.生前葬の注意点
生前葬は自由度が高い分、一般的な葬儀とは異なる部分が多く、事前に押さえておきたい注意点もあります。ここでは、とくに理解しておきたい3つの注意点を解説します。
香典の用意は基本的に不要
生前葬に参加される方にとって「香典を持参すべきかどうか」はとても気になるポイントです。
一般的に生前葬は、会費制や招待制を採用するケースが多く、香典を辞退する場合がほとんどです。主催者側は、招待状や案内状にも「香典辞退」の旨を明記しておくといいでしょう。
喪服は不要で平服で参加可能
生前葬には宗教的な儀式がほぼなく、明るい雰囲気で進行するケースが一般的です。そのため、従来の葬儀のように喪服や黒い礼服を着用する必要は基本的にはありません。
ただし、男性はスーツやジャケット、女性はスーツやワンピース、アンサンブルなど、ややフォーマルで落ち着いた装いがおすすめです。極端にカジュアルな服装や露出が多い服装は避けましょう。また、主催者側は、招待状に服装の案内やドレスコードを記載しておくと、参加者も安心できるでしょう。
生前葬を行っても逝去後の火葬は必要
生前葬を行ったとしても、逝去後の火葬や法的な手続きは必ず行わなければなりません。前述のように遺族が「改めて葬儀を行いたい」と希望すれば、二度目の式を行う可能性もあります。
あらかじめ逝去後の対応について家族と話し合い「自分が亡くなった後はどうしてほしいか」を明確にしておくことで、無用なトラブルや混乱を避けられるでしょう。また、逝去後の事務手続きや葬儀の扱いをどうするかなども、生前葬の計画とあわせて検討しておくのがおすすめです。
8.生前葬を行った著名人
最後に、生前葬を行った著名人をご紹介します。
水の江瀧子さん(俳優)
俳優として活躍した水の江瀧子さんは、生前葬のパイオニアとも呼ばれています。
森繁久彌さんを葬儀委員長に迎え、永六輔さんが司会を担当するなど豪華な顔ぶれが集結し、本人を前に個性的な弔辞が次々と読み上げられるなど、和やかでユーモアあふれる雰囲気で執り行われました。
数年後に水の江さんが亡くなった際は、近親者のみで葬儀を行ったとされ、生前葬と死後の葬儀が二重になった一例としても知られています。
高井研一郎さん(漫画家)
「釣りバカ日誌」などの作品で知られる漫画家の高井研一郎さんは、74歳の誕生日に初めて生前葬を行い、同業者や映画関係者など多彩な顔ぶれが参列したことで話題になりました。
その後、79歳で亡くなるまで計3回の生前葬を行い、回を重ねるごとに多くの人々が集まり、本人と直接交流を深められる場となったそうです。一般的には一度きりとイメージされがちな生前葬を、複数回にわたって実施したユニークな事例だといえます。
安崎暁さん(株式会社小松製作所・元社長)
株式会社小松製作所(コマツ)の元社長であった安崎暁さんは、末期がんと診断されたことを受けて「感謝の会」と名づけた生前葬を企画し、自ら新聞広告で参加者を募りました。
結果的に約1,000人もの参加者が集まり、安崎さんは車いすに乗って会場を回りながら直接感謝の言葉を交わしたといわれています。
「せっかく来てもらうなら楽しんで帰ってもらいたい」という思いを込めた催しは、生前葬が「死の準備」だけでなく「人生の区切りを華やかに祝う場」としても機能することを示す代表的な例といえるでしょう。
生前葬の事例としては、このほかにもアントニオ猪木さんや赤塚不二夫さん、小椋佳さん、ビートたけしさん、桑田佳祐さんなど、さまざまな分野の著名人が挙げられます。
9.生前葬を行う場合は、意義やメリット・デメリットを正しく理解しましょう
生前葬は、本人が元気なうちに主催し、直接感謝を伝えたり自分らしい式を企画できたりすることが大きな魅力です。一方で、周囲の理解を得づらい可能性や、亡くなったあとに改めて葬儀を行う可能性があるなど、注意すべき点もあります。
生前葬を行う場合は、こうしたメリット・デメリットをしっかりと理解したうえで、家族や親族と事前に十分な話し合いをしておきましょう。本人の意向や予算、家族の気持ちをすり合わせながら準備を進めることで、ご自身の人生を振り返り、感謝を伝えるためのかけがえのない式となるでしょう。
メモリアルアートの大野屋では、ご自宅のリビングのようなくつろぎ空間で、静かに温かく見送るための家族葬専用施設「フューネラルリビング」もご用意しています。
フューネラルリビングでは、アットホームな生前葬の実施も可能ですので、お気軽にご相談ください。