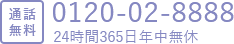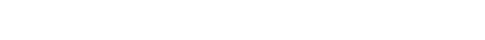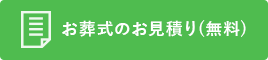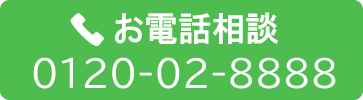デジタル遺品・デジタル終活とは? ネットユーザーの増加に伴いトラブルが多発中!生前にできる対策を徹底解説。
公開日:2025/02/19
更新日:2025/02/19
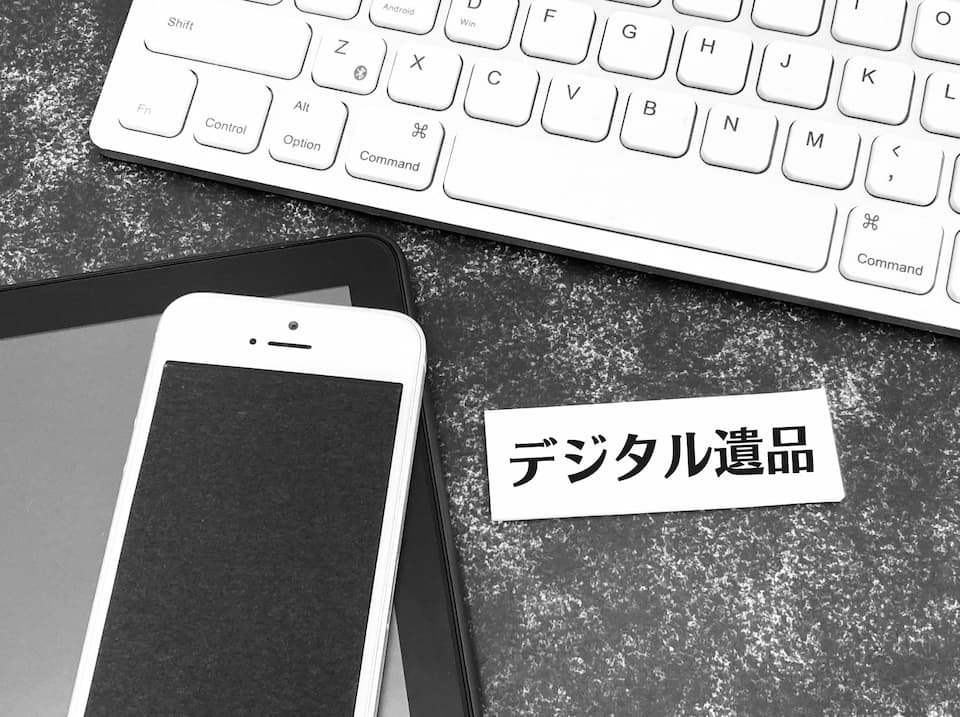
● デジタル遺品とは何か知りたい方
● デジタル終活を始めたい方
● デジタル遺品のトラブルが心配な方
1.デジタル遺品・デジタル終活とは?
パソコンやスマートフォンが普及し、多くの人が日常的にインターネットを活用している中で、「デジタル遺品」という言葉が生まれているのをご存知でしょうか。「デジタル遺品」に明確な定義はありませんが、一般的には、故人が生前に使用していたデジタル機器やオンラインサービスに残されたデータおよびアカウント(インターネット上のサービスを利用する際に必要な権利)などを指します。具体的には、スマートフォンやパソコン内の写真・動画・メールのほか、SNSのアカウント、ネットバンキングの情報、仮想通貨などが含まれ、「デジタル資産」や「デジタル遺産」と呼ばれる場合もあるようです。また、「デジタル終活」とは、一般的にデジタル遺品を生前に整理することを言います。
総務省の『情報通信白書(令和6年版)』によると、日本の個人インターネット利用率は86.2%に達しており、60代でも約87%、70代でも約66%が利用していると報告されています。また、2023年の総務省の調査では、日本の世帯において97.4%がスマートフォンなどのモバイル端末を、65.3%がパソコンを所有しているという結果になっています。インターネットを利用する世代の高年齢化が進み、デジタル機器が広く普及する中で、デジタル遺品の管理が今後ますます重要になっていくといえるでしょう。
この記事では、デジタル遺品とは何か、またデジタル遺品にまつわるトラブル事例やトラブルを防ぐための方法などについてご紹介します。「デジタル分野は苦手」、「専門用語はさっぱり...」という方にもできるだけわかりやすく解説しますので、ぜひお役立てください。
2.デジタル遺品の分類
デジタル遺品にはさまざまな種類があり、取り扱い方法や想定されるリスクもそれぞれ異なります。パソコンやスマートフォンといった形のあるものは比較的分かりやすいものの、インターネットにつながった状態(オンライン上)でやりとりされる契約やサービスは目に見えないため、「遺品」としてはイメージしにくいかもしれません。しかし、このオンラインのデジタル遺品の中にも、銀行や証券といった故人の資産に関わるもの、SNSのアカウントなど故人のプライバシーに関わる情報をはじめ、重要なものが数多く含まれていることがあります。ここでは、主なデジタル遺品の分類と、それぞれのリスクを合わせてご紹介します。
■ デジタル機器
パソコン、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラなどの端末
※その内部に遺された写真や動画、文書、連絡先などの情報も含まれます。
<リスク>
パソコンやスマートフォンには、連絡先や写真、契約情報といった重要なデータが集約されていることが大半です。しかし、パスワードによってロックされていることが多く、遺族がロックを解除することができないと、デジタル遺品の確認を進めることが困難になります。また、端末に個人情報や金融情報が残ったまま第三者の手にわたってしまうと、個人情報の流出や不正利用につながるおそれがあります。
■ ネット口座の情報
インターネット銀行、証券口座、FX口座、仮想通貨口座など
※「インターネット銀行」は「ネット銀行」とも呼ばれ、実店舗を持たず、インターネットを介した取引に特化している銀行のことをいいます。なお、近年は実店舗がある銀行でも、インターネットやスマートフォンのアプリなどから口座を開設できる他、紙の通帳を発行せずインターネット上で入出金を管理するタイプの口座も増えています。
<リスク>
遺族が口座の存在を知らずに資産を引き継げなくなったり、定期的に手数料が発生して資産が目減りしたりする可能性も。また、口座の存在を知っていても、ログインするためのIDやパスワードなどが分からないと開示請求を行うことができず、相続税の申告期限に間に合わなくなる場合があります。
■ ネット上のサービス
ホームページ、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、クラウドストレージなど ※「SNS」とは、インターネット上で登録者同士が交流して相互に情報を共有できるサービスのことで、LINEやX(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどが有名です。「クラウドストレージ」は、「オンラインストレージ」と呼ばれることもあり、インターネットを介してデータやファイルを保管や共有できる場所およびサービスのことを指します。代表的なものとしては、iCloud、Googleドライブ、Dropboxなどがあります。
<リスク>
ブログやホームページ、SNS上に、写真や住んでいる場所が分かる地名などが記載されていると、写真を悪用されたり、個人を特定されたりするリスクがあります。SNSアカウントを放置したままだと、なりすましやアカウント乗っ取り、不正アクセスなどの危険性も高まります。また、クラウドストレージなどは継続課金型のサービスとなっている場合が多く、解約しなければ利用料の引き落としが続きます。
3.デジタル遺品が引き起こすトラブル事例
デジタル遺品に関わるトラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。以下に主な事例をご紹介します。
■ データの流出
スマホやパソコンには、プライベートな写真や動画の他、銀行口座やクレジットカードの情報、関係者の連絡先など、重要なデータが記録されていることが大半です。もし、故人のパソコンやスマホからデータを削除せずに廃棄したり、何らかの理由で第三者にわたってしまったりした場合、データが流出して悪用されてしまうおそれがあります。
■ 遺影の写真がない
故人のパソコンやスマホのロックを解除することができないと、保管されている写真データを取り出すことができません。そのため、葬儀に用いる写真が必要な場合、手元にある適当な写真から引き伸ばしたり、古い写真を加工して使ったりしなければならなくなってしまいます。
■ 故人の友人・知人に連絡できない
かつては各家庭に手書きの電話帳などがあり、親戚や友人・知人の連絡先が家族で共有されていましたが、現代ではすべてスマホ内に集約されている方がほとんどでしょう。そのため、故人のスマホにアクセスできないため関係者の連絡先が分からず、葬儀のご案内ができないというケースも少なくありません。
■ データの消失
スマホのログインパスワードが分からないと、思いつくパスワードを何度も入力してしまう方がいらっしゃるかもしれません。しかし、特に故人がiPhoneを使用されていた場合は注意が必要です。iPhoneには、パスワードを10回連続で間違えるとデータが消去されてしまう機能があり、故人がその設定をオンにしていた場合、データが初期化されてしまう危険性があります。ロックが解除できないと慌ててしまいがちですが、むやみにパスワードの入力を繰り返さないようにしましょう。
■ 定額サービス(サブスクリプション料金)支払いが継続
定められた料金を定期的に支払うサブスク料金は、いったん契約すると、解約しない限り自動的に支払いが継続されるケースが一般的です。自動引き落とし先がクレジットカードや預金口座での引き落としになっていると、そのクレジットカードや預金口座が停止・凍結されることでストップすることもありますが、サブスクを放置したままにしている場合、通常料金に加えて遅延損害金を請求されるリスクもあるので注意が必要です。
■ 相続の問題が生じる
デジタル遺品は、IDやパスワードなど本人にしか分からない情報で管理されていることがほとんどです。そのため、相続人がその存在を見つけることが難しいという問題があります。さらに、デジタル遺品は想像以上に種類や数が多く、さらに手続きはすべてインターネット上で行われるケースが多いため、インターネットに不慣れな場合は手続きが煩雑になってしまいかねません。また、ネット口座やネット証券の株式、仮想通貨など金銭に関連する財産が遺されていた場合、遺族がその存在に気づかないまま放置してしまうと、相続税の申告漏れを指摘されたり、修正申告を行ったりと、相続人の負担になるばかりでなく、追徴課税などの損失を受けてしまう可能性もあります。
4.デジタル遺品のトラブルを回避するために
デジタル遺品が適切に管理されないと、遺された家族に余計な負担をかけるだけでなく、不要なトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。家族の負担を軽減するためにも、生前から必要な情報を整理しておくことが重要です。
■ デジタル終活のすすめ
終活とは、「人生の最期に備える準備」のこと。いつか訪れるお別れのときに備えて、ご自身の財産や身の回りの整理をすることをいいます。故人が亡くなった後、遺された遺族は深い悲しみの中で、葬儀の手配、関係者への連絡、公的手続き、相続の手続きといった、さまざまな慣れない手続きを行わなければなりません。このとき、もし故人が友人・知人の連絡先や相続対象となる財産などの情報を整理していなかった場合、遺族はその一つひとつを調べるところから始めなければなりません。もしものときに備えて、元気なうちから終活を進めることは、大切な家族の負担を軽減し、自分自身の不安を軽くすることにもつながります。終活の一環として、デジタル終活もあわせて進めておくと良いでしょう。
■ エンディングノートの活用
デジタル遺品の生前整理に、エンディングノートを活用するのも良い方法です。エンディングノートは、自分にもしものことがあったときに、遺された家族に伝えておきたいことを書き留めておくもので、書店などで購入することができます。さまざまな種類のノートが市販されていますが、デジタル遺品の生前整理には、銀行口座や契約しているサービスを一覧にまとめられるページが用意されているものが便利です。
デジタル遺品に関するトラブルは、パスワードが分からずに、故人のパソコンやスマホにアクセスすることができないために生じることが大半です。パソコンやスマートフォンなど所有している端末のロックを解除する方法は、必ず記入しておきましょう。SNSやメール、ネット口座、退会が必要なサービス等については、各サービスの名称と、「登録メールアドレス」、「ID」、「パスワード」などをリストにしておきます。中でも、銀行や証券口座は、相続の問題に関わるため、家族のためにわかりやすく記しておくことが重要です。生前からパスワードを共有することに抵抗がない場合は、家族やパートナーにのみ、ご自身のパソコンやスマートフォンにログインするためのパスワードを伝えておくとより安心です。
なお、メモリアルアートの大野屋では、ご希望の方にエンディングノートをお贈りしております。終活を考えたはじめた方に向け、お葬式の詳細や手続き方法がわかる資料と共に送付しますので是非ご応募ください。
■ デジタル遺品を処理する
生前に不要なデジタル遺品は処分しておくことは、遺された家族に負担をかけないためにも重要です。スマホで撮影した写真や動画を日常的に見返し、失敗した写真や不要になった画像を削除しておくだけでも生前整理につながります。また、不要なメールマガジンやサブスクリプションのサービスなどは解約しておくと良いでしょう。
古いパソコンやスマートフォン、携帯電話など、使っていないデジタル機器も処理しておきましょう。携帯電話やスマホは、公共施設や家電量販店などに設置されているリサイクル回収ボックスに入れたり、携帯電話ショップに持ち込んだりする他、中古販売ショップなどに売却することで処理できます。
ただし、スマホなどを処分するときは、必ず端末に残っているデータをすべて削除しておくことが重要です。お店などに持ち込めば初期化してくれると思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、持ち主が行わなければデータが消えることはありません。重大なトラブルにつながりかねませんので、忘れずにデータを削除しましょう。なお、端末を処分する前に、契約しているインターネットサービスなどの確認や解約を行うことも重要です。
5.主なウェブサービスのユーザー死亡時の対応先
ここでは、代表的なインターネットサービスにおける、利用者が亡くなった際の対応や問い合わせ先についてご紹介します。
【Googleヘルプセンター】
無料で利用できるGmailを利用している方も多いことでしょう。Gmailアドレスは、Googleのアカウントとして、データを保存するGoogleドライブや写真を保存するGoogleフォトをはじめ、さまざまなサービスのログインにも用いられている可能性があります。
ユーザーが死亡した際、家族は書類を揃えて申請することで、アカウントの閉鎖や資金やデータを取得するための開示要求を行うことができます。ただし、審査結果によっては開示されない可能性もあります。
Googleヘルプセンター(公式)【故人のアカウントに関するリクエストを送信する】
https://support.google.com/accounts/troubleshooter/6357590?hl=ja
なお、Googleには、「アカウント無効化管理ツール」という機能が用意されています。これを有効にすることで、一定の期間アカウントを利用していない状態が続いた場合、あらかじめ指定した他のユーザーにメールで通知してデータを公開したり、Google 側でデータを削除したりといった設定ができます。
【Apple】
iPhoneやMac、iCloudなど、故人がAppleの製品やサービスを使用していた場合は、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。Appleは「プライバシーは基本的人権」と宣言しており、ユーザーが死亡した場合はアカウントとアカウント内のコンテンツについて権利が消滅する、とiCloudの利用規約に明記しています。これは故人のプライバシーを重要視しているためです。
その上で、「亡くなったご家族のApple Accountへのアクセスを申請する方法」として、遺族が故人のAppleアカウントやその保管データへのアクセス、または削除を申請できる仕組みを用意しています。詳しくは以下のリンクからご確認ください。
Apple(公式)【亡くなったご家族のApple Accountへのアクセスを申請する方法】
https://support.apple.com/ja-jp/102431
なお、iOS 15.2、iPadOS 15.2、macOS 12.1以降では、自分の死後に自分のAppleアカウントに保管されているデータに信頼できる人がアクセスできるよう「故人アカウント管理連絡先」を追加することができますので、利用を検討してみるのも良いでしょう。
【LINE】
LINEアカウントは「一身専属」が原則であり、故人の友人・知人との関係やトーク内容も故人特有のものという考えから、ユーザー本人以外への譲渡や貸与、相続はできません。亡くなった方のアカウントに無断でログインすることは法律で禁じられています。そのため、遺族が本人に代わって故人のLINEにアクセスしたり、データを取得したりすることはできず、アカウント閉鎖の申請のみ可能です。何も手続きしなければ、そのままアカウントが残りますが、電話番号以外にメールアドレスなどを登録していない場合は、登録されている電話番号が新しいユーザーの登録用に使用されると、故人のアカウントが削除される場合があるので注意が必要です。故人のアカウント削除を希望する場合は、以下のフォームより問い合わせましょう。
LINE(公式)【アカウントを安全に保つために ~故人のアカウントを閉鎖する】
https://guide.line.me/ja/safety/account
【X(旧Twitter)】
Xでは、権限のある遺産管理人または故人の家族の申し出があった場合に、アカウントの停止を受け付けています。申請には、故人の情報、リクエストを送信された方の身分証明書のコピー、故人の死亡証明書のコピーといった詳細な情報をメールで送信する必要があります。
X(公式)【亡くなられたユーザーのアカウントについてのご連絡方法】
https://help.x.com/ja/rules-and-policies/contact-x-about-a-deceased-family-members-account
【Facebook】
Facebookでは、故人のアカウントを「追悼アカウント」に変更するか、アカウントを完全に削除するかのいずれかを選択することができます。追悼アカウントとは、利用者が亡くなった後に友達や家族が故人の思い出をシェアするための場所です。アカウントが追悼アカウントに変更されると、不正ログインなどを防ぎ、情報の安全を確保することができます。
Facebook(公式)【亡くなられた方のアカウントの管理】
https://www.facebook.com/help/275013292838654/
Facebook(公式)【追悼アカウントについて】
https://www.facebook.com/help/1017717331640041/
6.デジタル遺品に関する要点まとめ
● デジタル遺品とは、故人が生前利用していたデジタル機器やネットサービスのデータなどの総称。
・「デジタル終活」とは、万が一の際に備えてデジタル遺品を生前に整理しておくことを指す
・インターネットの普及が広がる現代において、今後ますます重要な課題となることが見込まれる
● 不要なトラブルを避けるためにも、デジタル遺品の生前整理をすることが大切。
・万が一の際に、家族がスマホやパソコンのロックを解除できるようにしておく
・ネット上の資産やサブスクなどの契約は、サービス名、ID、パスワードなどをリスト化する
・エンディングノートの活用も検討し、もしものときに家族に伝えたい情報をまとめておく
・自分に何かがあったときに、自分のアカウントを管理できる人を指定するサービスなどを利用する
大野屋テレホンセンターでは、デジタル遺品について具体的な対策等をご相談いただけます。
また、年会費無料の「もしも会員」でも便利な提携サービスを展開しております。