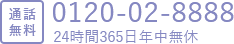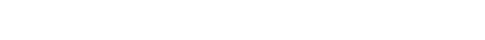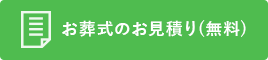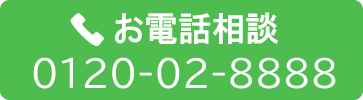葬儀保険(終活保険)とは?仕組み・メリット・選び方をわかりやすく解説
公開日:2025/03/04
更新日:2025/03/04

葬儀費用の負担を家族にかけたくないという思いから、葬儀保険(終活保険)への加入を検討する方が増えています。葬儀保険は、万が一のときにあらかじめ準備した保険金で葬儀費用をカバーするものです。高齢者でも加入しやすく、月々の掛け金が安く抑えられているのが特徴です。
本記事では、葬儀保険の基本的な仕組みや、メリット・デメリットを解説します。さらに、保険料の安さのからくりや、保険プランの選び方についても、わかりやすく紹介します。葬儀費用の備えを考え、家族への負担を軽減するための一助として、ぜひ参考にしてください。
● 葬儀保険の特徴や仕組みを知りたい人
● 葬儀保険はなぜ掛け金が安いのかを知りたい人
● 葬儀保険のメリットについて知りたい人
● 葬儀保険のデメリットについて知りたい人
● 葬儀保険の種類や選び方を知りたい人
1.葬儀保険(終活保険)とは?
葬儀を行うためには、ある程度の費用がかかります。生前にご自身で準備する方もいますが、実際には亡くなった後、ご遺族や子どもたちが葬儀費用を負担するケースが多く見られます。
そのため、残された家族が大切な貯蓄を切り崩さざるを得ない状況に追い込まれることを、不安に思う方も少なくありません。こうした経済的・精神的な負担を少しでも軽減するための仕組みが「葬儀保険」です。
葬儀保険の特徴・仕組み
葬儀保険は、被保険者がなくなった際に、あらかじめ設定された保険金が支払われ、葬儀費用をカバーする保険商品です。
「家族に金銭的な負担をかけたくない」と考える方にとって、葬儀保険は安心して終活を進めるための心強い手段といえるでしょう。
葬儀保険の契約金額は、数十万円から数百万円程度と比較的小規模なのが基本です。そのため、加入時の審査もシンプルで、高齢者でもスムーズに加入できるのが魅力です。さらに、月々の掛け金が数千円程度とリーズナブルなため、家計への負担も抑えやすくなっています。
生前葬を行う動機や理由
近年では、ライフステージの多様化に伴い「元気なうちに支えてくれた人へ感謝を伝えたい」「十分にお礼を伝えられないまま、亡くなりたくない」と考える方が増えています。
なかには定年退職や古希・喜寿などの年齢を迎え、人生の節目として「生前葬」を検討されるケースも少なくありません。
また、従来の葬儀は短い日数で準備をする必要があり、遺族の負担が大きくなる傾向があります。そのため、生前葬であらかじめ式を行っておき、死後の葬儀を縮小・簡略化しようと考える方もいます。
さらに、エンディングノートの作成などで「終活」が普及している今、最後のセレモニーを、自ら自分らしく企画したいと考える方が増えているのも事実です。
2.葬儀保険はなぜ安い?費用のからくり
一般的な生命保険や医療保険と比較すると、葬儀保険の掛け金がリーズナブルに設定されています。その理由の1つは、葬儀保険が「少額短期保険」に分類されるからです。
「少額短期保険」とは?
「少額短期保険」とは、保険金の上限が定められており、通常は最大でも300万円程度までの保障しか受けられない保険のことを指します。
葬儀費用の相場は、一般的には100万〜200万円前後です。そのため、葬儀保険は「少額短期保険」の枠内で設計されています。保障金額が限定されているため、リスクも相対的に低く、その結果、保険料も安価に設定されるのです。
この仕組みのおかげで、葬儀保険は、月々の掛け金が数千円程度に抑えられており、家計に負担をかけず、必要最低限の葬儀費用を備えることが可能です。
関連記事:
お葬式の費用
3.葬儀保険はどんな人に向いている?
葬儀保険は、いざというときに葬儀費用を迅速に用意できる安心の備えとして、特に以下のような方におすすめです。
・葬儀費用を事前に準備しておきたい人
・高齢で生命保険に新規加入できない人
・遺族に金銭的な負担をかけたくない人
・預貯金が少なく、すぐに葬儀費用を捻出できない人
4.葬儀保険のメリット
葬儀保険の大きなメリットは「高齢者でも加入しやすいこと」と「掛け金が安いこと」の2点です。詳しく見ていきましょう。
高齢者でも加入しやすい
葬儀保険は、従来の生命保険や医療保険と異なり、健康告知のハードルが低い商品が多く存在します。
健康告知とは、保険加入時に自分の健康状態や過去の病歴を申告する手続きのことです。一般的な保険では詳細な情報が求められるのに対し、葬儀保険では詳細な健康診断や告知書の提出が不要で、簡易なチェックで済むのが基本です。
そのため、高齢者でもスムーズに加入でき、安心して葬儀費用の備えをすることができます。
掛け金が安い
葬儀保険の大きなメリットは、月々の保険料がリーズナブルな点です。一般的な葬儀保険の掛け金は、契約者の年齢やプランによっても前後しますが、月々約2,000円から3,000円程度が相場となっています。
高齢になってから、新たに100万円や200万円といった大きな貯蓄を積み立てるのは難しいケースが多いですが、毎月数千円という保険料であれば、家計の中で工夫をすれば捻出できる金額でしょう。
さらに、万が一の際には、受取人に迅速に保険金が支払われるため、ご遺族が葬儀費用の支払いに困ることなく、経済的な負担を大幅に軽減できます。
5.葬儀保険のデメリット
葬儀保険は、加入のしやすさや保険料の安さといったメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。ここからは、事前に知っておきたい葬儀保険のデメリットについて詳しく解説します。
保険の責任開始期がある
葬儀保険であっても、一般的な保険と同様に「責任開始期(責任開始日)」があります。責任開始期とは、保険契約の成立後、実際に保障が有効になる日のことで、保険会社が契約内容を最終確認し、リスク評価を完了するための期間として設けられています。
通常、責任開始期は契約成立日から約1ヶ月後に設定されることが多く、契約日からすぐに保障が開始されるわけではありません。そのため、契約日から責任開始期の間に万が一の事態が発生しても、保険金は支払われません。
葬儀保険を契約する際には、この空白期間について十分に把握しておくことが大切です。
掛け捨ての可能性がある
葬儀保険は、更新型の掛け捨てタイプが主流です。つまり、1年や2年といった期間で契約を更新し、支払った保険料は返金されません。
そのため、長期的に加入していると、支払った保険料の総額が実際に受け取る保険金額を上回ってしまう可能性もあります。
途中解約のリスクがある
葬儀保険は、途中解約した場合、解約返戻金がほとんどない、または全く受け取れないのが一般的です。すでに支払った保険料が戻ってこないため、解約時のリスクは十分に理解しておきましょう。
加入年齢によっては保険料が高い
葬儀保険は、加入する年齢や契約時期によって、保険料の負担が大きくなる場合があります。高齢で加入すると、保険事故の確率が高まるため、月々の掛け金や支払総額が上昇する傾向があります。一方で、比較的若いうちに加入してしまうと、長期契約となり支払総額が大きくなるリスクもあります。
葬儀保険を検討する際は、保険料と保険金のバランスを十分に考慮し、加入のタイミングを慎重に見極めることが大切です。
保険会社が倒産した場合
一般的な生命保険では「生命保険契約者保護機構」という仕組みがあります。これは、保険会社が万が一倒産した場合に、契約者が受け取るはずの保険金が、一定額まで保証されるシステムです。
しかし、葬儀保険は少額短期保険に分類されるため、生命保険契約者保護機構の対象外となっています。つまり、万が一葬儀保険を提供する会社が倒産してしまった場合、保険金が支払われない可能性があるのです。
このため、葬儀保険に加入する際は、会社の経営状況や信頼性をしっかりと確認し、倒産リスクを回避できるような信頼性の高い保険会社を選ぶことが重要です。
6.葬儀保険の主な種類は2つ
葬儀保険には、大きく分けて「保険金定額型」と「保険料一定型」の2種類があります。それぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。
保険金定額型
保険金定額型の葬儀保険は、契約時に決定された保険金額がその後も基本的に変わらず維持されるタイプです。葬儀費用として必要な金額が明確な場合、ご遺族に確実な金額が保証されるというメリットがあります。また、受け取る保険金自体は固定されるため、将来の葬儀費用の見通しを立てやすく、長期的な保障内容が変わらない点が大きな強みといえます。
ただし、保険料は年齢に応じて上昇する傾向にあり、加入時点では低くても高齢になると掛け金が増加するのが一般的です。
保険料一定型
保険料一定型の葬儀保険は、契約時に決定された毎月の保険料が、その後も変動しないタイプです。支払額が一定なので、家計の負担を予測しやすく、収入が限られる場合でも安定して加入を続けることができます。
しかし、年齢の上昇に伴い、受け取れる保険金額は徐々に減少します。そのため、保障される金額は初期に設定された額よりも低くなる可能性があります。
7.葬儀保険の選び方のポイント
葬儀プランには多様な商品が存在するため、ご自身の目的やライフスタイルに合った保険を選ぶことが大切です。
ここからは、葬儀保険を選ぶ際に確認しておきたいポイントについて解説します。
保険金の支払いタイミング
葬儀は急な出費となることが多いため、万が一の際に保険金が迅速に支払われるかどうかは重要なポイントです。
葬儀保険は、商品ごとに書類審査や手続きの期間が異なりますが、一般的には必要書類が整ってから翌営業日〜最長5営業日以内に支払われます。保険金をすぐにご遺族が葬儀費用として充てられる仕組みが整っているか、事前によく確認しておきましょう。
月々の支払額は無理のない範囲か
葬儀保険は、月々数千円程度の掛け金が一般的ですが、ご自身の家計に与える影響を考慮することが必要です。
支払額が無理のない範囲で設定されているか、また長期間にわたって継続できるかをしっかりと見極め、無理なく保険料を捻出できるプランを選びましょう。
保障内容が希望に合っているか
葬儀保険は、保障される金額やカバー範囲が商品ごとに異なります。ご自身が希望する葬儀費用の準備額や、その他必要な費用(たとえばお布施や会場費など)に対して十分な保障があるかを、具体的な金額で確認することが重要です。
受取人を自由に設定できるか
保険金の受取人は、自動的にご遺族が指定される場合もありますが、家族内の事情や意向に合わせ、自由に設定できる保険商品も存在します。
受取人の自由設定が可能なら、たとえば配偶者だけでなく、子どもや信頼できる第三者に指定することもでき、万が一の際に柔軟な対応が可能です。
告知・診断書の要否
葬儀保険は一般的な生命保険に比べ、健康告知のハードルが低い商品が多いですが、保険によっては告知書や診断書の提出が必要な場合もあります。
ご自身の健康状態や必要書類の入手方法、審査の厳しさなどを確認して、スムーズに加入できるかどうかを判断しましょう。
責任開始期の確認
前述の通り、葬儀保険にも保険契約が成立した後、実際に保障が開始される「責任開始期」が設定されているのが一般的です。
契約日から一定期間、保障が有効にならない空白期間が存在するため、契約時にその期間や条件を十分に理解し、万が一の事態に備えた計画を立てましょう。
途中解約時の返戻金の有無を確認
葬儀保険のデメリットでも解説しましたが、葬儀保険は多くの場合、掛け捨て型で途中解約しても返戻金が受け取れない場合がほとんどです。
加入期間中にやむを得ず解約する可能性があるならば、返戻金の有無についてもチェックしておきましょう。
8.葬儀保険の注意点
葬儀保険は、終活に備えるための有用な手段ですが、契約にあたっては、理解しておくべき注意点も存在します。
税務上の取り扱いや、加入時の情報提供など、ご自身が不利益を被らないために必要なポイントを解説します。
葬儀保険は課税対象
葬儀保険で受け取る保険金は、一般的な生命保険とは異なり、税務上の取り扱いに注意が必要です。具体的には、受け取った保険金が所得税や相続税の課税対象となる場合があります。
通常、生命保険には非課税枠が設けられていますが、葬儀保険は少額短期保険に分類されるため、この非課税措置の対象外となることが一般的です。そのため、保険金を受け取った際には、税金が差し引かれる可能性があります。
保険金にどの程度の税金がかかるか、適用される税率や控除措置などを事前に確認し、必要であれば税務上の対策も講じておくことが重要です。
被保険者の告知義務
葬儀保険は、一般的な生命保険に比べて健康告知のハードルが低く、比較的簡易なチェックで加入できるのが特徴です。
しかし、告知義務自体が完全に免除されるわけではありません。たとえ告知内容が簡略であっても、虚偽や重要な情報の未記載が発覚すると、契約時に提示した内容が信用されなくなり、保険金の支払いが拒否されたり、契約が解除されたりするリスクがあります。
契約時に提示された告知事項は、後日の保険金支払いの根拠となります。そのため、自己の健康状態や病歴を正確に記載することが、トラブルの回避となります。
9.葬儀保険の加入はメリット・デメリット、注意点を理解して検討しましょう
葬儀保険は、万が一に備えて葬儀費用を迅速に用意できる、終活の有用な手段です。高齢者でも加入しやすく、掛け金もリーズナブルに設定されています。一方で、保険金の支払いタイミングや掛け捨て型のリスク、途中解約時の返戻金の有無、さらには税務上の取り扱いや告知義務など、知っておくべき注意点も存在します。
各プランの特徴や支払い条件、保障内容を十分に比較・検討し、ご自身のライフプランや家計状況に合った保険を選ぶことが、遺族の負担を軽減し、安心した終活に繋がります。
もしものとき、大切なご家族に葬儀費用の負担をかけたくないとお考えの方や無理のない範囲で葬儀費用を準備しておきたい方には、メモリアルアートの大野屋の葬儀保険がおすすめです。
保険料や保障内容については、専任の相談員がご希望やご状況を詳しくお伺いし、最適なプランをご提案いたします。まずはご自身の備えについて、お気軽にご相談ください。