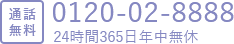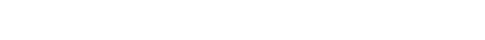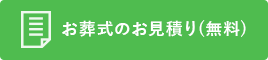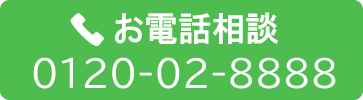納骨堂(室内墓苑)とは? 種類や特徴、メリット・デメリット、費用相場や選び方のポイントまで徹底解説
公開日:2025/03/19
更新日:2025/03/19

● 納骨堂(室内墓苑)について知りたい方
● 納骨堂(室内墓苑)のタイプ選びで迷っている方
● 納骨堂(室内墓苑)のメリット・デメリットを知りたい方
1.納骨堂(室内墓苑)とは?
納骨堂とは、遺骨を安置するための屋内施設のことをいいます。屋外に墓石を建立する一般的なお墓とは異なり、建物の中に納骨スペースを設けている点が特徴です。なお、「室内墓苑」は「室内墓所」や「室内墓地」とも呼ばれ、建物内にあるお墓のことを指します。
納骨堂そのものは古くから存在し、もともとは納骨までの間に、お寺などで一時的にご遺骨を預かるための施設でした。しかし、最近では従来のお墓に代わる新しい供養の形として広く知られるようになりました。
その背景には、少子高齢化や核家族化の進展、都市部における土地不足の問題、宗教や先祖供養に対する価値観の変化などが挙げられます。従来のお墓は家族代々受け継ぐことが前提でしたが、少子高齢化が進む現代では、お墓の継承問題が深刻化しています。「お墓を守る後継者がいない」、「子どもに負担をかけたくない」という思いから、維持管理の手間が少ない納骨堂や室内墓苑を選択する方も増えているようです。また、都市部では墓地が不足し、土地価格の高騰も相まって、従来型の墓地を購入することが難しくなってきました。加えて、宗教観や供養のあり方が多様化していることから、特定の宗派に属さずに利用できる施設が注目を集めています。このような社会の変化を背景に、現代の価値観やライフスタイルにマッチした新しいお墓として、納骨堂(室内墓苑)を選ぶ方が増加傾向にあります。
2.納骨堂(室内墓苑)と他のお墓との特徴比較
日本のお墓は大きく分けて4種類あり、納骨堂(室内墓苑)はそのうちの一つです。ここでは、それぞれのお墓の一般的な特徴をご紹介します。
■ 納骨堂(室内墓苑)
屋内に納骨スペースを設けた施設で、ロッカー式・仏壇式・自動搬送式など様々なタイプがあります。利用期間は契約するプランによって異なり、期間に応じた使用料が必要です。
■ 一般墓
寺院や公営・民営の墓地など、屋外に墓石を建立して遺骨を納める日本の伝統的なお墓の形式で、家族代々受け継がれることが一般的です。お墓の継承者がいて管理費を支払う限り、永年利用できます。
■ 永代供養墓(合祀墓)
複数の遺骨を一緒に埋葬し、寺院や霊園が永代にわたって管理・供養を行うお墓。屋内・屋外、納骨方法や個別区画の有無などは寺院や霊園によって様々です。永代使用料と永代供養料がかかります。
■ 樹木葬
墓石を建立せず、樹木を墓標としてその周辺に遺骨を埋葬するタイプのお墓です。屋外の公園のような自然環境にあることが多く、利用期間は管理者によって異なります。利用期間に応じた使用料の他、墓標などをつける場合はオプション料金が必要です。
3.納骨堂(室内墓苑)の種類と特徴、費用相場
納骨堂には様々な形式があり、特徴やメリットもそれぞれ異なるため、どのタイプが最適かは個人の価値観や参拝する方の状況などによっても変わります。ここでは、納骨堂の主な3つの種類について、特徴や目安としての費用相場もあわせてご紹介します。
■ ロッカー式納骨堂
ロッカーのような扉付きの収納スペースに、ご遺骨を安置するタイプの納骨堂です。コンパクトな造りながら、個別の納骨スペースを確保することができます。費用は10万円程度からと経済的負担が少ない点もメリットですが、一定期間を経過した後は合同墓へ移行するケースが多いようです。
■ 仏壇式納骨堂
屋内の仏壇のようなスペースにご遺骨を安置し、遺影や位牌を安置することができる納骨堂です。家族ごとに独立した区画が設けられていて、自宅の仏壇に近い形で供養できるので、家族でお参りしやすい納骨堂といえるでしょう。料金相場は、個人の場合で30万円程度、家族3〜5人で100万円程度とされており、ロッカー式に比べると費用が高くなる傾向があります。
■ 自動搬送式納骨堂(カード式・電子制御)
お参りの際に、専用ICカードを指定の場所にかざしたり、タッチパネルを操作したりすることで、ご遺骨が収蔵スペースから自動で参拝ブースまで運ばれてくる形式の納骨堂です。「ビル型」や「マンション型」、「可動型」などと呼ばれることもあります。最新のシステムで管理されており、費用相場は、1柱につき約50〜200万円となっています。
メモリアルアートの運営する『常光閣』の室内のお墓もこの自動搬送式納骨堂となります。
■ 個別墓(墓石型)タイプ
従来のお墓に近い形で供養できる納骨堂です。大きく以下の2種類に分けられます。
(1)墓石を建てるタイプ
屋内にある墓地区画に小型の墓石を建立し、遺骨を安置する形式です。屋内でありながら従来のお墓のように個別に墓石を持つことができ、家族など複数人の供養が可能です。ただし、スペースが限られているため、一般的な屋外の墓地ほど大きくすることはできません。墓石の建立費用がかかる場合もあり、一般的な費用相場は100〜350万円程度です。
(2)参拝スペースに遺骨が搬送されるタイプ
従来の墓石供養と現代的な自動搬送システムが融合した形式です。個別の墓地区画を持たず、専用カードをかざすとご遺骨が収蔵庫から自動的に参拝ブースまで移送され、墓石とともにお参りできるタイプです。費用は、一般的に80〜150万円程度とされています。
4.納骨堂(室内墓苑)の費用内訳
前述の「3. 納骨堂(室内墓苑)の種類と特徴、費用相場」にて、納骨堂(室内墓苑)を選択した場合の総費用の相場について簡単に触れましたが、では、具体的には、どのようなことに費用がかかるのでしょう。ここでは、利用にかかる費用の主な内訳や納骨堂(室内墓苑)の種類ごとの相場をご紹介します。立地や設備、プランなどによっても大きく変動しますので、あくまでも一般的な目安として参考にされてください。
■ 初期費用
契約時に必要となる費用。納骨スペースの使用や供養に関する料金など、基本的な費用が含まれます。
【永代供養料】
永代供養とは、施設側が永代にわたって遺骨の管理や供養を行ってくれることをいいます。納骨堂(室内墓苑)の初期費用には、永代供養料がプランに含まれていることが一般的です。
【区画使用料】
個別区画を一定期間使用するための費用です。ロッカー式や仏壇式、個別墓タイプなど、種類によって価格が異なり、立地や設備の充実度によっても変動します。区間使用料は基本的に契約時に一括で支払い、一定期間を過ぎると、ご遺骨は合祀墓に移される点に注意しましょう。
【厨子(ずし)】
「厨子(ずし)」とは、ご遺骨の収納に使われる専用の入れ物のこと。施設ごとにデザインやサイズが異なり、種類によって費用が変わる場合があります。
【銘板(めいばん)費用】
厨子の前に設置する、故人の名前や戒名を刻むプレートのこと。石や金属など、素材の種類や刻む内容によって金額は異なります。
【参拝カード】
自動搬送式の納骨堂では、遺骨を保管している厨子を参拝ブースに移動させるためにICカードが必要です。このカード発行に費用がかかる場合があります。
■ 初期費用の他にかかる費用
納骨堂(室内墓苑)を利用する上で、初期費用とは別に、継続的に支払いが必要となる費用があります。
【年間管理料】
施設の維持管理や清掃、設備のメンテナンスなどに充てられる費用です。毎年支払う施設がほとんどですが、契約者本人による生前契約などの場合は、年間管理料を一括払いすることもあります。
【納骨式の法要料】
納骨の際は、僧侶による読経や法要を行うことが一般的です。このときに読経供養の謝礼としてお渡しする費用を「法要料」といいます。複数のご遺骨を収納する場合、法要料は納骨式を行う都度必要です。
【納骨堂のタイプ別:一般的な価格帯の目安】
| 納骨堂のタイプ | 費用相場 |
|---|---|
| ロッカー式納骨堂 | 10〜50万円 |
| 仏壇式納骨堂 | 30〜100万円 |
| 自動搬送式納骨堂 | 50〜200万円 |
| 個別墓タイプ | 80〜350万円 |
5.納骨堂(室内墓苑)のメリット
ここでは、納骨堂(室内墓苑)の代表的なメリットについてご紹介します。
■ 天候に左右されずにお参りできる
納骨堂(室内墓苑)は屋内施設のため、季節や天候を気にすることなくお参りできます。雨の日でも傘を差す必要がなく、足元がぬかるんだり、線香やお供え物が濡れたりする心配もありません。また、夏の暑い日や冬の寒い中でも快適にお参りできます。
■ アクセスが良好
都市部の駅から近い場所に建てられることが多く、公共交通機関を利用して気軽にお参りできます。郊外や山の近くに建てられることの多い従来の墓地に比べて、お参りしやすい環境が整っているといえるでしょう。
■ 継承者不要で永代供養が可能
少子高齢化や核家族化の進展により、お墓の継承者がいないケースも増えています。納骨堂(室内墓苑)の多くは、継承者がいなくなった場合も、施設側が責任を持って永代供養をしてくれるため安心です。
■ 手ぶらでお参りできる
多くの納骨堂(室内墓苑)では、お参りに必要な備品があらかじめ用意されています。そのため、仏具などを持ち運ぶ必要がなく、当日忘れ物をして慌ててしまう心配もありません。中には、館内でお花を購入できる施設もあり、仕事帰りや外出の途中などに気軽に立ち寄ることができて大変便利です。
■ 掃除など管理の手間がかからない
納骨堂(室内墓苑)は屋内にあるため、一般的なお墓のような雑草の手入れや墓石の掃除などは不要です。また、施設のスタッフが日々清掃や管理を行っているため、常に清潔な環境が保たれています。
■ 宗教や宗派を問わない施設が多い
一般の墓地は、お寺の檀家である方がお墓を継承している場合が大半で、基本的には檀家ではない他宗派の供養は行いません。一方、納骨堂(室内墓苑)では宗教・宗派を問わずに利用できる施設が多いため、寺院の檀家になっていない方や、宗教に捉われない自由な供養を望む方にも適しています。
■ 設備が充実している施設が多い
一般的に、納骨堂(室内墓苑)は段差のないバリアフリー構造になっている施設が多く、トイレや冷暖房も完備されているので快適にお参りできます。また、セキュリティ体制も整っており、遺骨を自動搬送するシステムなど、最新の設備を備えた施設もあります。
■ 少人数利用の場合は費用を抑えられる
一般的な墓地に比べると、費用を抑えられるというメリットがあります。ただし、スペースが限られているため少人数の利用に適しており、個人や夫婦のお墓を希望する方にとっては良い選択肢といえるでしょう。
6.納骨堂(室内墓苑)のデメリット
多くのメリットがある反面、納骨堂(室内墓苑)には従来のお墓とは異なる点も多いため、利用にあたって注意すべきことがあります。デメリットもあらかじめ理解した上で、自分に合った供養の形を選びましょう。
■ 従来のお墓参りとは雰囲気が異なる
屋内施設である納骨堂(室内墓苑)は、スペースの制約もあり、一般的にイメージされるような従来の屋外でのお墓参りとは趣が異なります。伝統的な供養を行いたい場合、この点はデメリットといえるでしょう。
■ 継承者がいない場合は一定期間を過ぎると合祀される可能性がある
納骨堂や室内墓苑は契約期間が定められており、一定期間を過ぎると合祀墓へご遺骨を移されることが一般的です。永代供養型の場合、契約期間は33回忌までとされることが多く、その後は合同供養になる可能性があるため、合祀に抵抗がある方は事前に確認が必要です。
■ 一部の施設ではお供え物の制限がある
火災防止や衛生管理の観点から、お花や飲み物、食べ物などのお供え物を制限している施設もあります。故人が好きだったものをお供えできないケースもあるので、契約時に確認しておきましょう。
■ 家族の気持ちにも配慮が必要
現代的な供養方法として需要が高まっている一方、親族の中には「やはり従来のようなお墓のほうが良い」と考える方がいらっしゃるかもしれません。十分に話し合い、全員が納得できる選択肢を選びたいものです。
■ 建物の耐用年数などの懸念
建物の老朽化や災害時の対策も気になることの一つです。長期間にわたって供養を続けることが可能か、耐震性や修繕計画、建て替え時の対応といった点も、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
■ お墓参りシーズンは混雑しやすい
多くの人がお参りに訪れるお盆やお彼岸などの時期には、施設内が混雑しやすくなります。特に自動搬送式の納骨堂では順番待ちが発生する場合もあり、混雑時は屋外の墓地に比べてスムーズにお参りができないと感じるかもしれません。
■ 収納できる遺骨の数、デザインや彫刻に制限がある
限られたスペースを活用するため、遺骨の収納数には制限があります。また、墓石や納骨室のデザインが一律で決められていることも多く、彫刻などでオリジナリティを出したい方には適さない場合があります。
■ お線香を焚けないことが多い
防火管理のため、お線香やロウソクの使用が禁止されている施設も少なくありません。線香の煙や香りの風情とともに故人を偲びたいという方は、施設を選ぶ際に必ず確認しましょう。
7.納骨堂(室内墓苑)のまとめ
● 納骨堂(室内墓苑)は現代のライフスタイルに合った新しいお墓。
・ 様々なニーズに合致する新しい供養の形として近年関心が高まっている
・ 需要の増加に伴い、最新システムを備えた施設など種類も多様化
・ 納骨堂のタイプ、施設の立地や設備、プランなどによっても費用は異なる
● 納骨堂(室内墓苑)は、このような方におすすめです。
・ お墓の継承者がいない方、お墓参りや管理の負担を減らしたい方
・ 季節や天候を気にすることなく快適にお参りしたい方
・ 駅の近くなど、都市部でアクセスしやすいお墓を探している方
・ 管理が行き届いた清潔な環境で故人を供養したい方
・ 特定の寺院の檀家になっていない方、宗教や宗派にこだわらない方