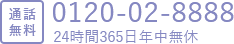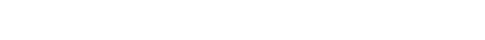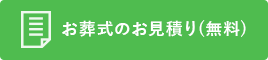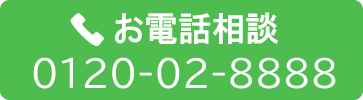故人の貯金は葬儀費用に使える?利用方法と注意点、仮払い制度についても解説
公開日:2025/03/27
更新日:2025/03/27

葬儀費用の準備で「故人の貯金を利用できるのか?」と不安に思う方も多いでしょう。故人の預貯金を葬儀費用に充てることは、法律上問題なく認められていますが、実際には銀行口座の凍結、仮払い制度の手続き、相続放棄の判断など、さまざまな注意点が存在します。
そこで本記事では、葬儀費用の相場や内訳を解説するとともに、故人の預貯金を利用する際の具体的な方法と注意点を解説します。故人の預貯金以外で葬儀費用を準備する方法についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
● 故人の貯金を葬儀費用に充てられるか知りたい人
● 故人の貯金から葬儀費用を支払う際の注意点を知りたい人
● 葬儀費用を支払うために故人の貯金を引き出す方法を知りたい人
● 故人の貯金以外で葬儀費用を準備する方法を知りたい人
1.葬儀費用に故人の貯金を充てることは可能
葬儀を行うためには、まとまった費用が必要になります。故人の預貯金を活用すれば、急な出費による遺族の経済的負担を軽減できます。
ただし、銀行が口座名義人の死亡を把握すると口座は凍結され、通常の引き出しができなくなります。そのため「仮払い制度」などの手続きが必要となる点に注意しましょう。また、引き出した金額の使途によっては、相続放棄に影響を及ぼす場合もあります。
葬儀の費用に故人の預貯金を充てる際は、手続きや注意点などを十分に理解しておくことが大切です。
2.葬儀費用の相場
葬儀費用は、葬儀の形式や規模によって大きく異なります。以下に、主な葬儀の種類ごとの費用相場と内訳、支払い方法を紹介します。
葬儀の種類ごとの費用相場
・一般葬(120万〜200万円):通夜・告別式を行い、参列者も多い形式
・家族葬(80万〜150万円):家族・親族中心で小規模に実施
・一日葬(40万~100万円):通夜を行わず告別式に集約
・直葬(20万〜50万円):通夜や告別式を行わず、火葬のみ
葬儀費用の内訳
費用には、以下の項目が含まれるのが一般的です。
・葬儀社費用:基本サービス料や運営費用
・会場費:葬儀場などの使用料
・祭壇費:祭壇の設営費用
・飲食接待費:参列者へのおもてなし費用
・寺院費用(お布施):僧侶へのお布施や寺院使用料
・遺影写真費用:故人の写真や映像制作費用
そのほかにも、交通費やオプションサービス費用などが発生する場合もあるため、葬儀費用の見積もりを取る際は内訳を十分に確認しましょう。
葬儀費用の支払方法
葬儀費用の支払方法には、さまざまなケースがあります。以下に代表的な支払方法を紹介します。
喪主が支払う
一般的には喪主が全額または主要な部分を負担します。喪主は故人の意思や家族の合意に基づき、支払いの調整を行います。
施主が支払う
喪主が葬儀を執り行う責任者であるのに対して、費用負担を担う人を「施主」といいます。喪主と施主の両方がいる場合は、葬儀費用を施主が支払うのが一般的です。ただし、近年の葬儀では、喪主が施主を兼任しているケースが多く見られます。
香典を活用して支払う
参列者からいただいた香典を、葬儀費用の一部に充てる方法です。香典は弔意の証としてだけでなく、費用補填の役割も果たします。
相続人の間で分担して支払う
複数の相続人がいる場合は、費用を各自の相続分に応じて分担することができます。事前に話し合い、負担割合を明確にすることで、後々のトラブル防止につながります。
故人の相続財産を活用して支払う
故人の預貯金や不動産などの相続財産から葬儀費用を賄う方法です。故人の相続財産を活用する場合、遺族自身の手元資金に依存せずに支払いが可能ですが、相続手続きや税務上の確認が必要となる点に注意しましょう。
3.故人の貯金から葬儀費用を支払うときの注意点
残された家族に経済的負担をかけたくないという思いから、ご自身の葬儀費用のための預貯金を用意している方も少なくありません。
しかし、故人の預貯金を葬儀費用に充てる際は、事前に理解しておくべき注意点があります。ここでは、故人の預貯金を葬儀費用に充てる際の注意点を解説します。
銀行が口座名義人の死亡を知ると銀行口座が凍結される
故人が亡くなると、銀行は遺族からの連絡や新聞のお悔やみ欄、残高証明の申請などを通じて死亡の事実を把握し、速やかに口座を凍結します。
凍結された口座からは通常の引き出しができず、仮払い制度や正式な相続手続きが必要となります。金融機関ごとに凍結のタイミングや解除の手続きが異なるため、早めに確認し、必要な書類(戸籍謄本、死亡診断書、相続人全員の印鑑証明など)を準備しておくことが重要です。
相続放棄ができなくなる可能性がある
故人の預貯金を葬儀費用に充てた際、状況によっては相続放棄が認められなくなるケースがあります。
<相続放棄が認められなくなるケース>
・必要以上に豪華な葬儀を行った場合
・葬儀費用として必要以上の支出を出した場合
・葬儀以外の費用として使用した場合
・預貯金の仮払い制度を利用した場合
豪華な葬儀や必要以上の支出は、故人の財産を無条件に使用したと見なされ、相続の「単純承認」と判断される可能性があります。「単純承認」とは、故人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐ相続方法であり、単純承認とみなされると相続放棄ができなくなります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、葬儀費用を適切に抑えるとともに、費用の使途を明確にして領収書や明細書などの証拠を確実に保管しておくことが大切です。
また、後述する「仮払い制度」を利用した場合も、引き出した預貯金の使途によっては「単純承認」とみなされる場合があるため注意しましょう。
葬儀費用の相続税控除対象に注意
故人が残した遺産から相続税を計算する際、葬儀費用の一部も控除対象として認められています。つまり、葬儀にかかった費用は、相続税の計算から差し引くことができるため、遺族の税負担を軽減する効果があります。
ただし、葬儀費用のすべてが控除対象になるわけではありません。一般には、通夜・告別式、火葬料、埋葬料など、葬儀に直接関係する費用は相続税控除の対象となります。一方で、喪服代、香典返し、法要費用などは、葬儀とは直接関係がないと判断され、控除対象外となるケースが多いとされています。
葬儀費用を正しく控除対象として申告するためには、各費用項目の内訳を明確に記録し、領収書や明細書などの証拠をきちんと保管することが重要です。相続税の控除について不明な点があれば、税務の専門家に相談してみましょう。
4.葬儀費用を払うために故人の貯金を引き出す方法
故人の預貯金から葬儀費用を引き出すためには、状況に応じて適切な方法を選ぶ必要があります。ここでは、各方法のポイントと具体的な手続きについて詳しく解説します。
口座凍結前であれば遺族も引き出せる
故人が亡くなった直後は、まだ銀行が死亡情報を受け取っていない場合もあり、凍結前にキャッシュカードなどを利用して必要な金額を引き出せることがあります。
この方法では、早期に引き出しを行うことで、凍結後の手続きにかかる手間や時間を省いて迅速に資金を確保できます。ただし、引き出した金額は「相続財産」とみなされるため、ほかの相続人との間で必ず事前に合意形成を図り、引き出し額や使途について記録を残すことが重要です。
急いで遺産分割協議を行う
故人の銀行口座が凍結されると、通常の引き出しはできなくなるため、相続人全員で遺産分割協議を速やかに行うことが必要になります。
遺産分割協議が円滑に進めば、必要書類(戸籍謄本、死亡診断書、印鑑証明、遺産分割協議書など)をそろえた上で、銀行に対して正式な相続手続きを行い、凍結解除後に預貯金の引き出しが可能です。
預貯金の仮払い制度を利用する
遺産分割協議が完了していなくても、故人の預貯金から一定額を「仮払い制度」で引き出すことが認められています。
仮払い制度では、各金融機関ごとに定められた上限(一般的には150万円まで)や、故人の預金残高と相続人の法定相続分に基づいた計算方法が適用され、必要な葬儀費用のみを先に受け取ることが可能です。
ただし、仮払い制度を利用する際は、戸籍謄本や相続人の印鑑証明書、金融機関指定の申請書などが必要になります。また、仮払い制度は遺産分割協議の完了前に実施されるため、制度利用後の正式な相続手続きとの整合性にも注意しましょう。
家庭裁判所の許可を得て引き出す
仮払い制度の上限を超える金額が必要な場合、または相続人の間で合意が得られずに仮払い制度が利用できない場合は、家庭裁判所に「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立てる方法があります。
この手続きは、家庭裁判所がほかの相続人の権利や利益を害さないと認めた場合に限り、故人の預貯金から必要な金額を一時的に引き出すことを許可するものです。
ただし、申立てには、詳細な事情説明や必要書類の提出が求められ、手続きに数週間から数ヶ月かかることもあります。そのため、急ぎの葬儀費用の支払いには適さない場合もあります。手続き開始前に法律専門家と十分に相談し、適正な対策を講じましょう。
5.故人の貯金以外で葬儀費用を準備する方法
故人の預貯金以外にも、葬儀費用を確保するためにはさまざまな手段があります。生前の資金計画や公的支援、保険制度、互助会などがその代表例です。
ここでは、故人の預貯金以外で葬儀費用を準備する方法について解説します。
葬儀費用を預金口座から事前に引き出しておく
生前に、ご本人が葬儀費用として必要な金額を預金口座から引き出し、現金で保管しておく方法です。故人が亡くなったあとの急な手続きや口座凍結のリスクを回避できるという大きなメリットがあります。
ただし、現金の管理は紛失や盗難のリスクが伴うため、信頼できる方法で保管し、家族間で使用目的や保管場所を明確にしておくことが重要です。
自治体の葬祭サポートについて調べておく
葬儀費用の負担が難しい場合は、自治体の給付金や補助制度を活用して費用を抑えることができます。
たとえば、国民健康保険加入者には「葬祭費」、健康保険加入者には「埋葬料」または「埋葬費」が支給され、金額は3万円〜7万円程度が一般的です。申請には保険証や葬儀の領収書などが必要となり、期限は葬儀翌日から2年以内です。
また、市民葬や区民葬など、自治体が提携業者と提供する低価格プランがある地域もあります。内容や条件は自治体ごとに異なるため、事前に窓口で確認しておくといいでしょう。
葬儀保険や生命保険に加入しておく
万が一に備えて、葬儀費用を保険で準備しておくことも有効な方法です。とくに「葬儀保険」は、葬儀費用に特化した少額短期の保険商品で、月々の保険料が数千円程度と手頃な点が特徴です。加入年齢の幅も広く、持病があっても加入しやすい商品が多いため、高齢の方でも無理なく備えられます。
死亡時には、保険金が比較的早く支払われるため、預貯金が凍結されていても、葬儀費用をスムーズにまかなえます。一般的な生命保険と合わせて活用すれば、堅実な備えができるでしょう。
ただし、葬儀保険は掛け捨て型が一般的です。加入期間によっては、支払額が保険金額を上回る可能性もある点に注意してください。
メモリアルアートの大野屋では、葬儀保険のご案内もしております。保険料や保障内容については、専任の相談員がご希望やご状況を詳しくお伺いし、最適なプランをご提案いたします。葬儀保険について詳しく知りたい方は、お気軽にご相談ください。
葬儀信託や互助会へ加入しておく
葬儀信託は、故人の預貯金を事前に銀行に信託し、葬儀費用を直接葬儀社へ支払う仕組みです。口座凍結や相続手続きの手間を軽減できるため、スムーズに葬儀を進めることができます。
また、互助会に加入すると、毎月一定額を積み立てることで、必要な時にサービスという形で葬儀費用を軽減できます。
メモリアルアートの大野屋では、"もしもの時"に葬儀や仏事全般のサポートや割引特典を受けられる無料会員制度「もしも会員」をご用意しています。
もしも会員にご加入いただくと、お葬式やお墓・お仏壇の費用優待だけでなく、相続や遺品整理といった終活支援、日常生活に役立つ提携サービスの割引など、多彩な特典が利用可能です。
6.故人の貯金の取り扱いについては注意点をよく理解しておきましょう
故人の預貯金は葬儀費用に充てることが可能です。ただし、口座の凍結や相続放棄への影響など、事前に理解しておくべき注意点もあります。トラブルを避けるためには、預貯金の引き出し方法や使途を事前に把握し、領収書などの記録をしっかり残すことが大切です。
また、自治体の支援制度や葬儀保険、葬儀信託といった代替手段についても理解しておくことで、万が一のときに備えることができます。葬儀費用に関する不安がある場合は、専門家や葬儀社に相談しながら準備を進めておきましょう。
メモリアルアートの大野屋では、ベテランスタッフが常時、葬儀や法要のご相談も承っております。お気軽にご相談ください。